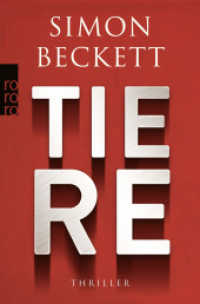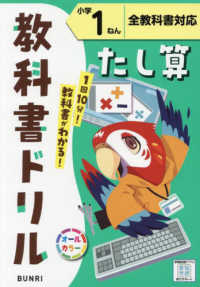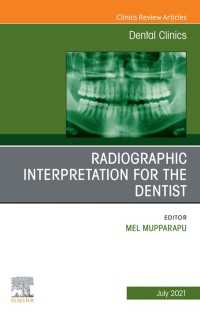出版社内容情報
異民族による巨大帝国支配。
天下を統合した思想の変遷に迫る。
“野蛮な夷狄“が新たな中華文明を拓いた
中華思想は文明の優劣で人々を区別する発想である。文明のある世界を中華とし、その周辺には野蛮な夷狄がいる。そして夷狄は中華に何も残さなかったものだと長らく考えられてきた。しかし注意深く歴史をみていくと、夷狄であるはずの遊牧民はむしろ中華文明の形成に積極的に関わり、新たに持ち込み、主体的に選別し、継承してきたことがわかる。中華文明拡大の要因は、あらゆるものを内部に取り込んで膨張していく性質にある。逆に言えば、気づけば夷狄も中華になっているのだ。本書は、中国史を遊牧民の視点から捉えなおすことにより、中華の本質に迫る一冊である。
内容説明
“野蛮な夷狄”が新たな中華文明を拓いた。異民族による巨大帝国支配。天下を統合した思想の変遷に迫る。
目次
第一章 中国史にとっての遊牧民
第二章 中華文明の成立と夷狄
第三章 中華古典世界と夷狄
第四章 中華と夷狄の対峙
第五章 夷狄を内包する中華世界
第六章 夷狄による中華の再生
第七章 新たな中華の誕生
著者等紹介
松下憲一[マツシタケンイチ]
1971年、静岡県生まれ。北海道大学大学院文学研究科博士後期課程東洋史学専攻修了。博士(文学)。愛知学院大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サアベドラ
37
文明の始まりから安史の乱あたりまでの遊牧諸集団と漢人の関わりをまとめた新書。2025年刊。著者は選書メチエで拓跋鮮卑の本を書いた人で、本書は実質的にその前史を扱った本と言える。中華文明はその誕生の時点から草原の世界の影響を受けており、北方の遊牧集団と争いまたは共存し、彼らとの相互作用のなかで「中華民族」が形成されていった。中華文明として一定の完成を見た唐王朝に続く諸征服王朝は、近世アジアに普遍的ないわゆる農牧二元的「中央ユーラシア型国家」の体制を採るようになる。中国史をユーラシア史に接続する好著。2025/09/05
よっち
28
中華文明の形成に積極的に関わり、新たに持ち込み、主体的に選別し、継承してきた遊牧民たち。中国史を遊牧民の視点から捉えなおすことにより、中華の本質に迫る1冊。中国の王朝交代と文明の中で、遊牧民はどのような役割を果たしてきたのか。中国王朝の成立と夷狄との関係に始まり、匈奴国家成立による対立関係、匈奴の臣従と五胡十六国時代の夷狄による中華の再生、隋唐時代の中華再統一に至るまでの過程を扱っていて、同化していった遊牧民が持ち込んだものもまた少なからず中華に影響を与える形で成立していったことが伺えて興味深かったです。2025/06/06
kk
26
図書館本。唐朝までの歴史を辿りながら、周辺民族との様々なインタラクションの中で中華の形が変容を遂げてきたことを示そうとしているものの如し。その意気に感心。他方で、紙幅の大半は北方騎馬民族の消長や文化的・社会的特徴、それら民族興隆の背景などに充てられている印象。先史文明の淵源や華夷思想の濫觴などは別として、周辺から中華への影響については、椅子だのテーブルだのに触れているのみ。南方諸民族と南朝との関係などはスルー。問題意識とプロダクトの間に些かのギャップなしとしない感。著者よりも寧ろ編集者に更なる工夫を期待。2025/07/30
ta_chanko
23
農牧境界地帯と接する華北において、遊牧民と農耕民のさまざまな形での接触が繰り返され、その中で「中華」世界が形成され、また変容してきた。周も秦も西方の遊牧民を起源とする勢力。当初は遊牧民を蔑視する意味はなかったが、儒教思想の広がりとともに遊牧民を「夷狄」とする中華思想が形成された。五胡十六国~北魏~北朝時代には遊牧民が華北の農耕民を支配し王朝を建て、両者の文化が混交することで新たな「中華」が成立=隋唐帝国。父兄の妻を子弟が娶ったり、妻や母の権力が強い(馮太公や則天武后)のは遊牧民の伝統。2025/08/13
さとうしん
20
新石器時代から唐代まで、牧畜民あるいは遊牧民の文化や活動を忠臣とする中国史。著者の主張を強く押し出すというよりは近年の研究の成果を踏まえての概説というスタンスで好感が持てる。筆者の専門の範囲外の時代も要所をちゃんとつかんでいるように思う。本書では時代を新石器~西周、春秋~漢、魏晋~唐の3つのステージに分けているが、末尾で示唆されている通り、宋代以後の遼や金など「征服王朝」はそれまでの胡漢融合のあり方とは様相が異なってくると感じる。2025/05/09