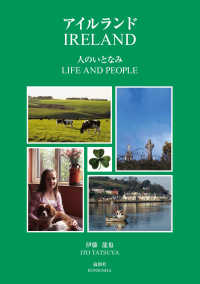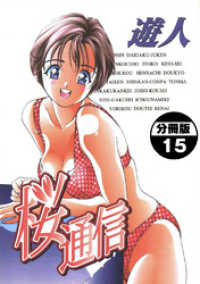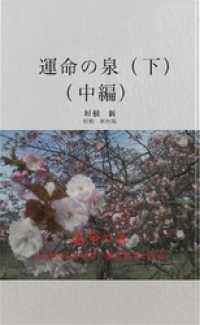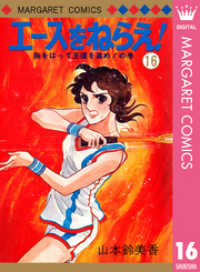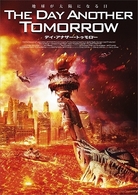出版社内容情報
幕府も倒幕派も、
競って英語を学び始める──
・伊藤博文(長州)…密航留学で攘夷から開国へ
・大隈重信(佐賀)…各国憲法を英語で読了
・榎本武揚(幕府)…多言語を操る国際通
福沢諭吉、勝海舟、西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允、坂本龍馬、森有礼、
徳川慶喜、ジョン万次郎、寺島宗則、渋沢栄一、夏目漱石……などが躍動!
江戸幕府を倒し、新しい「日本」の形を模索した明治維新。水面下では、言葉をめぐって「もう一つの闘い」が繰り広げられていた。迫りくる西洋列強と外国語で交渉できなければ植民地にされかねない。まともな教科書も辞書もない時代、サムライたちは必死に西洋語を学び、欧米に密航留学した。漢学、蘭学に加え、英語、独語、仏語が乱立する中、なぜ英語が新しい国家を創る原動力となりえたのか? 英語教育史の第一人者が、これまで語られてこなかった視点から幕末・明治に光を当てる。