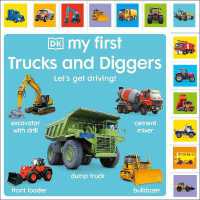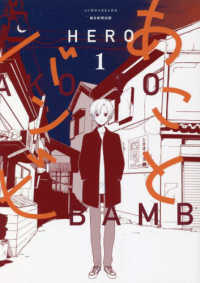出版社内容情報
すみっこはよくない。
孤立したアリは、なぜ早死にするのか? 分子生物学で、その謎を解く!
集団をつくり、他者との関わりをもって生きていこうとする性質である「社会性」……本書では、昆虫が苦手だった筆者がすっかり魅了され、10年以上にわたって見つめてきた、アリの不思議な世界をご紹介します。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
130
タイトルから、生態学的な研究、ひいては集団行動に対する社会学的な成果を期待すると裏切られる。本書は、もっと真面目な分子生物学の取り組みである。著者は、孤立アリの早死が、活性酸素の増加であり、それが脂肪体に蓄積していることを突き止める。さらに、細胞内のmRNAを網羅的に解析するトランスクリプトーム解析によって、遺伝子レベルでその仕組みを明らかにしようと奮闘する。小さなアリの内臓をすり磨り潰したり、細胞を染色したり、解剖をするなど、昆虫研究の困難さと闘う若き科学者としての著者の姿勢に、心からエールを送りたい。2025/08/15
ネギっ子gen
68
【アリは他の個体との社会的な交流に依存して生きている】社会性昆虫であるアリは、ヒトの生態と似ていて、他者と関わって社会の中で生きている。では、社会から出て“ぼっちになったアリ”はどうなるのか。生態学からアリ社会の謎を解く書。アリの生態学を研究する著者は“孤立アリ”という研究テーマに出会い、<同じ孤立といっても、アリとヒトではまったく違う仕組みが媒介をしているのかもしれないし、何らかの共通の遺伝子や細胞に行き着くのかもしれません。そこまで行き着いたときにはじめて共通点と相違点を明確にする>ことができると。⇒2025/10/04
うえぽん
54
産総研主任研究員によるアリの社会性研究に係る著作。アリは女王アリ・労働アリのカーストの存在などから霊長類とは区別される真社会性を持つとされ、個体間の栄養交換や、年をとるとコロニーから外勤に変わる齢依存的な労働分業を行うとする。1944年の孤立アリの早死に係る論文の検証を行い、壁際での滞在という行動変化が脂肪体での活性酸素の発生とそれによる短寿命に関係していることを立証。労働アリが女王アリから離れるのは子孫を残す機会を失わせるもので、ヒトの孤立とは異なるが、孤立の影響の探究にアリが役立つのか関心を持ちたい。2025/05/24
本詠み人
51
私たち霊長類とは違う真社会性(子孫をできるだけ多く残すことを目的に女王アリのみ生殖役割を与え、その他の労働アリは卵巣を持ちつつも生殖しない)アリの研究をされている著者さん。アリをぼっちにすると、顕著に寿命が縮むことが昔から知られているが、何故そうなのか著者が仮説をあげ、脂肪細胞に溜まる活性酸素が寿命の短さの原因でそれを取り除けば他のグループアリと同じ寿命となることを突き止めた。ただ、最近の研究では活性酸素は悪いばかりではなく記憶の形成に必要とのこと。アリの研究が人間にどのように応用されるのか続きが知りたい2025/12/27
山口透析鉄
30
市の図書館本より。書評記事を見て借りたものと記憶しています。ショウジョウバエなどは実験の例が膨大にありますが、アリはそれほどでもなく、留学中に苦戦していた時期に孤立アリの寿命がやたら短くなる理由を調べようとなってからの話が書かれています。 実際は女王アリがいないアリの種類もいるようです。単性生殖メインの種は研究に使いやすいようです。 孤立化させられた労働アリに幼虫を与えると寿命が延びるには仕事があるからでしょうか?アリの労働分担の方法等はまだ謎のようです。外仕事は老齢の労働アリの担当ですが。(以下コメ欄)2025/09/15