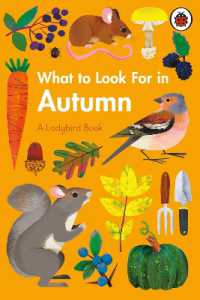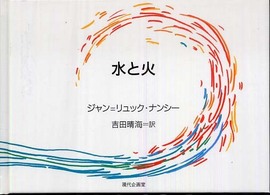出版社内容情報
加入率の低下や担い手の高齢化により、存続の危機に瀕する町内会。それは自治や共助の伝統か、時代遅れの遺物か。隣近所から日本社会の成り立ちを問いなおす。
内容説明
加入率低下や担い手の高齢化により、存続の危機に瀕する町内会。回覧板、清掃、祭り、防災活動など、活動は多岐にわたる。そもそも参加は任意であるはずなのに全戸加入が原則とされてきた、このふしぎな住民組織はいつどのようにして生まれたのか。それは共助の伝統か、それとも行政権力の統治技術か。明治地方自治制、大衆民主化の時代から戦中・戦後まで、コミュニティの歴史を繙くことで、この国の成り立ちがみえてくる。問題の本質をとらえ、再生の手がかりを探るための必読書。
目次
第1章 危機にある町内会(町内会が消える?;首都圏近郊の状況 ほか)
第2章 町内会のふしぎな性質(町内会とは何か;町内会の特異性 ほか)
第3章 文化的特質か、統治の技術か(町内会=文化の型論;スープと味噌汁の違い ほか)
第4章 近代の大衆民主化―労働者と労働組合、都市自営業者と町内会(明治地方自治制から町内会体制へ;明治地方自治制の動揺 ほか)
第5章 町内会と市民団体―新しい共助のかたち(グローバル化と都市自営業者層の衰退;町内会体制がもっていた可能性 ほか)
著者等紹介
玉野和志[タマノカズシ]
1960年石川県金沢市生まれ。東京都立大学人文学部卒業。東京大学大学院社会学研究科博士課程中退。社会学博士。東京都老人総合研究所、流通経済大学、東京都立大学を経て、放送大学教養学部社会と産業コース教授。専門は都市社会学・地域社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
購入済の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あすなろ@no book, no life.
うえぽん
1.3manen
たまきら
山口透析鉄