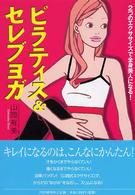出版社内容情報
戦前昭和に酷似するコロナ禍の日本。天皇をシンボルに社会の同調圧力とポピュリズムで作動した強制力の弱い国家総動員体制の失敗を教訓に、危機の政治を考える。
内容説明
今回の緊急事態をこの昭和一〇年代に起きた出来事と比較するとどうか。非常に共通性が高いと指摘することが可能だ。驚くほどに似ていると言っても過言ではない。特に新体制とは類似性が高い。ともにポピュリズム的要素が強く、政府を突き動かす形で国民の方から緊急事態を作り出しているからである。
目次
第1章 岐路に立つ象徴天皇制
第2章 天皇周辺の「大衆性」―近衛文麿と宮中グループ
第3章 戦前型ポピュリズムの教訓
第4章 コロナ「緊急事態」で伸張したポピュリズム
第5章 ポピュリズムと危機の議会制民主主義―菅内閣論
第6章 大正期政治における大衆化の進展
第7章 関東大震災と「ポピュリズム型政治家」後藤新平
第8章 「大正デモクラシー」から「昭和軍国主義」へ
第9章 太平洋戦争への道程とポピュリズム
終章 ポピュリズム型同調社会と政治的リーダーの形成
著者等紹介
筒井清忠[ツツイキヨタダ]
1948年生まれ。帝京大学文学部長・大学院文学研究科長。東京財団政策研究所主席研究員。専門は日本近現代史、歴史社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
金吾
23
下からの同調圧力により政治が左右される状態を戦前とコロナ期を対比しながら書いています。田中内閣と菅内閣の比較は面白かったです。2025/10/29
ほうすう
8
大まかに書くと大正から昭和戦前期を題材とした論考集。いくつかの章から成り立っておりそれぞれ緩やかなつながりはあるものの各章は比較的独立している。本としてのまとまりはともかく個々の章としては読みやすく面白いものであった。コロナ禍と戦前日本の共通点、下からの行き過ぎた全体主義に対する警告というのが多分一番言いたいことではあると思うしその点については異論はない。歴史学でありながら社会学的視点を持っていたのも面白い。本旨と異なるかもしれないが個人的には大正期の政争も面白そうだなと深堀したくなる要素が垣間見えた。2024/12/01
めっかち
4
筒井清忠博士の論考集。ポピュリズムという観点からなされる昭和史と令和日本の分析はどれも興味深い。特に、昭和の「全体主義」とコロナ禍で進められた「自粛」という名の「全体主義」の比較は興味深い。なるほど、反日左翼諸君の言う通り、日本は戦前から何も学んでいないらしい。それから、筒井博士の問題としてあげるのは「革新的平等主義」。国内的貧富の格差と、世界的な人種差別に対する憤懣こそ、大東亜戦争への道を作ったと見るのは妥当だろう。2023/11/30
あるまじろの小路
4
大正時代から太平洋戦争に至る日本社会の動きと令和コロナ現象との共通点を探る、大変興味深い一冊でした。対米開戦で本格的に戦争体制に入るまでは政府による上からの統制は名目的なもので、むしろ世間の同調圧力によって個人の行動がコントロールされたという点は、まったく今のコロナに対する姿勢と同じでぞっとしますね。さらには、そんな国民の傾向を後押ししたのがマスコミの煽りであったという事実。本質的に日本社会は全く変わっていないことがよくわかりました。2022/12/06
鴨長石
3
コロナ禍は戦時中の空気に近いのではと感じていた。周りにあまりそのような見方をする人はいなかったが、ようやく同じような考えをする人を見つけた。最近は戦争を直接経験した人がほぼいなくなり、「一般市民は戦争を当時から嫌がっていた」という風潮が強いが、実際は対コロナと同じで、勝てない相手にもかかわらず戦ってやっつけようという空気だったのではないか。2024/11/01


![[緊急度別]人を助ける災害&トラブル英語1000 地震・水害・事故・病気から命を](../images/goods/ar2/web/imgdata2/47890/4789019268.jpg)
![毎年出る!センバツ40題 理系数学標準レベル[数学1・A・2・B・3]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/40103/4010348674.jpg)