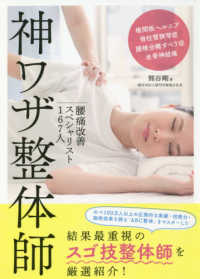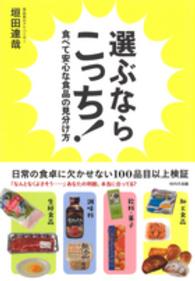出版社内容情報
関東大震災、金融恐慌、戦時下経済から戦後復興、高度成長、バブル、失われた30年へ。歴史に学ぶことはなぜ難しいのか? 株式市場、金融・経済の歴史を追う。
内容説明
はじまりは、株式市場でどの銘柄も軒並み暴落した一九二〇年。その後、関東大震災、昭和恐慌に直面し、戦争へと突き進む中、日本の株式市場、金融システムは様々な政策のもと、揺れ動いていくことになる。戦後復興、高度成長、バブル、「失われた三〇年」といま続く流れはどのように導かれていったのか。経済・金融政策と人々の思惑はいかに影響を与え合うのか。歴史の教訓を見誤らないためにこの百年を振り返る。
目次
第1章 瓦落と震災
第2章 金融恐慌とプルーデンス政策
第3章 国際金本位制をめぐって
第4章 コーポレート・ガバナンスの変容
第5章 高度成長への道
第6章 自由化とバブル
第7章 今そこにある歴史
終章 百年の歴史からみえてきたもの
著者等紹介
横山和輝[ヨコヤマカズキ]
1971年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(経済学)。一橋大学経済学部助手、東京大学日本経済国際共同研究センター研究員を経て、名古屋市立大学大学院経済学研究科准教授。専門は金融論、経済史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
90
日本の金融史を物語的な手法で解説してくれて比較的無味乾燥な分野に楽しみを与えてくれて読みやくなっています。ナラティブ経済学(ロバート・シラー)を読んだので具体的な適用がこのような感じになっているのですね。また同じ年に生まれた二人の女性を登場させているのも面白い試みでした。最後の参考文献もかなり充実して私には参考になります。2022/03/09
k5
50
旅行先で地銀の看板や本店の写真を撮るという、謎のマイブームが訪れているので読んだのですが、その観点からいくと期待はずれだったかも。幕末から武家や商人が金融システムを作る過程に興味があった私に対して、関東大震災後の復興金融から始まるミスマッチ。ただ、まっとうに金融史を語るならその方が正解ですわな。金融史に並行して、二人の有名な女性の個人史も語られるなど、読ませる工夫もある本です。関心が大正以降に移ったときまた読もう。2025/01/25
スプリント
8
日本の金融史と不世出の女優原節子と日本のお母さん森光子の生涯をクロスして構成は秀逸です。 記憶の定着を助けてくれます。2021/10/24
gokuri
7
大正から現在までの金融の歴史をつづった書。主に金融恐慌と、その時代における金融政策について、史実を分かりやすく記しており、金融政策に乏しい私にとっても、日本史を思い出しながら読み進むことができたのは、当時の社会情勢、政治背景なども工夫してちりばめられているおかげ。 膨大な資料をもとに、取りまとめられており、著者の経済学者としての力量を垣間見た気がする。2022/01/28
駒場
7
淡白になりがちな長期の通史を、当時の芸能界の花形俳優(森光子と原節子)と社会の受容のエピソードを交えながら書くという「ナラティブ」に焦点を置いた点がユニーク。昔は「金融やばくね?」というナラティブが地域的にゆるゆる伝播していたが、今は一瞬だな〜。昭和のバブル(瓦落)と恐慌を経て市場・銀行の機能によるコーポレートガバナンス強化が進みかける→戦時経済で政府統制に舵を切る→戦後は銀行が強い影響力を持つ→平成バブルで再び市場型の統制へ→しかしまた世界金融恐慌……金融は永遠に暴れ馬ですよ2021/09/12
-
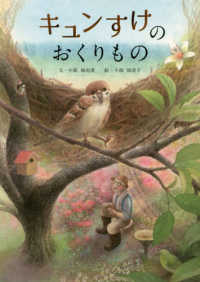
- 和書
- キュンすけのおくりもの