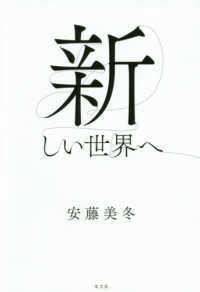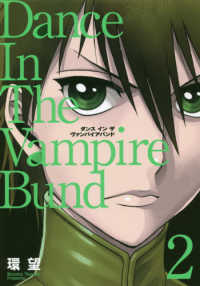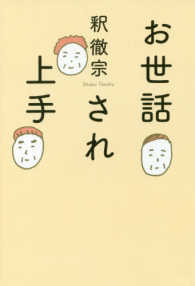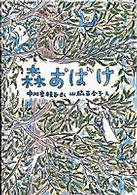出版社内容情報
事実や自己、他者をゆがんだかたちで認知する現象、バイアス。それはなぜ起こるのか? 日常のさまざまな場面で生じるバイアスを紹介し、その緩和策を提示する。
内容説明
物事を現実とは異なるゆがんだかたちで認識してしまう現象、バイアス。それはなぜ起こるのか、どうすれば避けられるのか。本書では、現実の認知、他者や自己の認知など日常のさまざまな場面で生じるバイアスを取り上げ、その仕組みを解明していく。探求の先に見えてくるのは、バイアスは単なる認識エラーではなく、人間が世界を意味づけ理解しようとする際に必然的に生じる副産物だということだ。致命的な影響を回避しつつ、それとうまく付き合う方法を紹介する画期的入門書。
目次
第1章 バイアスとは何か
第2章 バイアス研究の巨人―カーネマンとトヴァースキー
第3章 現実認知のバイアス
第4章 自己についてのバイアス
第5章 対人関係のバイアス
第6章 改めて、バイアスとは何か
著者等紹介
藤田政博[フジタマサヒロ]
1973年生まれ、神奈川県出身。東京大学法学部卒業、同修士課程修了。北海道大学大学院文学研究科修士課程修了。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。政策研究大学院大学准教授などを経て、関西大学社会学部教授。専門は、社会心理学、法と心理学、法社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
96
私の読解力の限界だろうが「バイアスとは何か」の本質に到達しないまま読了する。多様なバイアスがあることは理解できた。それらは「認知のゆがみ」という心理学的現象であり、行動経済学として意思決定に影響することも、司法制度に作用することもわかった。しかし、認知のゆがみは、受容されるべきか、矯正すべきか、その正体が納得できない。人類がヒューリスティック的な判断力を獲得したことがバイアスを生み出したと言う。でも、ポジティブ幻想、楽観バイアスに塗れた政府のコロナ対応が、ヒューリスティックスのせいだとは、とても思えない。2021/07/28
あおでん@やさどく管理人
35
様々なバイアスが平易な具体例とともに紹介されており、人間はこれほどまでに世界をゆがめて見ているのかと思うほど。だがこれも、生きるか死ぬかの危険と隣り合わせで、集団で暮らしてきた、かつての人間の生存戦略に根ざすのではないかと述べられている。バイアスを完全になくすことはできない。最終章で述べられている「バイアスを和らげる方法」はまだ研究途上だという印象もあったが、少なくとも「こういうバイアスがある」と知っておくことは無駄にはならない。2022/04/25
おせきはん
31
バイアスについて学術的な研究成果をもとに解説されています。自分にバイアスがあることは、ある程度認識していましたが、バイアスを否定的に考えていた自分にバイアスというよりも偏見があったことにも気づきました。バイアス自体が悪いわけではなく、自分のバイアスを自覚したうえで、よく考えることが大切だと思いました。2022/01/21
テツ
20
自身が客観的に世界を見つめ、その上で公平に判断を下していると大抵の人間は勘違いをしているけれど、そこには必ず何かしらのバイアスがかかっている。それは必ずしも悪いことではないし、その影響下にあるからといって必ず間違いを犯してしまうわけでもない。ただ基本的には全てにおいて認知は歪んでいるのだということを知識として頭に入れておきさえすれば、極々稀にそうした歪みから生じる悲劇をギリギリで止めることができるのではないかと感じる。何もかも自覚するところから始まる。2022/03/27
紫の煙
18
バイアスとは、認知のゆがみである。一言で言うとそうなのだが、意識していないのがバイアスなのだから、結局よく分からない。紹介されている事例それぞれは納得できても、何か判断する時に役に立つたつだろうか。後から考えれば、バイアスが働いていたと思うのだろう。2021/08/20