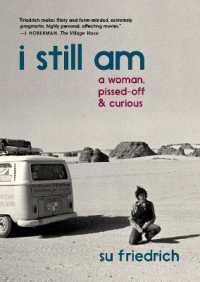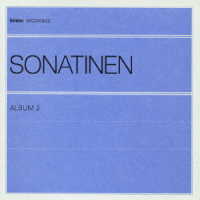出版社内容情報
学力格差の実態はどうなのか? それを克服するにはどうすればよいのか? 「学力保障」の考え方や学校の取り組みなどを紹介し、解決に向け考察する。
内容説明
学力格差を克服するのに必要なのは、すべての子どもの基礎学力を下支えする「学力保障」である。学力低下論争への考察を皮切りに、学力について考えを深め、学力格差の実態を考察。「学力保障」をカギとして、「効果のある学校」「力のある教育委員会」の実例を紹介し、学力格差克服の方法を探っていく。よりよい未来をつくるために、これからの学校、公教育の進むべき道を示唆する、学力格差研究の集大成。
目次
第1章 学力向上vs.学力保障―問題の構図(学力低下論争の勃発;二こぶラクダの発見 ほか)
第2章 学力をどう捉えるか―フィロソフィー(日本語としての学力;戦後の学力観 ほか)
第3章 学力格差はどうなっているか―サイエンス(格差・教育格差・学力格差;学力格差の国際比較 ほか)
第4章 学力格差をどう克服するか―アート(世界での動き;「伝統的な学力」対「新しい学力」 ほか)
第5章 公教育システムをどう再構築するか―展望(どんな社会をめざすのか;学校の夢 ほか)
著者等紹介
志水宏吉[シミズコウキチ]
1959年生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。博士(教育学)。大阪教育大学講師、東京大学助教授などを経て、大阪大学大学院人間科学研究科教授。専門は、教育社会学・学校臨床学・共生学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
りょうみや
totuboy
げんざえもん
yu12418
とりぞう