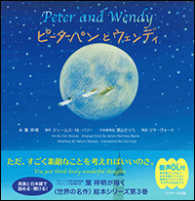内容説明
「平成」の三十年間で、日本とアフリカを取り巻く状況は激変した。経済成長が止まり、国力が低下する日本。一方、かつて日本人が時に哀れみの視線を注ぎながら援助していたアフリカでは、多くの国で経済成長が持続し、平和と民主主義の定着が進む。二〇五〇年に世界人口の四人に一人を占める「豊穣の大陸」と、少子高齢化に喘ぐ日本はどう向き合えばよいのか。アフリカとの関係構築に、日本再生の手がかりはあるか?篠田英朗氏との対談「アフリカに潜む日本の国益とチャンス」も収録。
目次
1 アフリカを見る アフリカから見る(発展するアフリカ;アフリカはどこへ行くのか;世界政治/経済の舞台として;アフリカから見える日本)
2 アフリカに潜む日本の国益とチャンス
著者等紹介
白戸圭一[シラトケイイチ]
1970年生まれ。立命館大学大学院国際関係研究科修士課程修了。毎日新聞社でヨハネスブルク特派員、ワシントン特派員などを歴任。2014年に三井物産戦略研究所に移り、欧露中東アフリカ室長などを経て、2018年から立命館大学国際関係学部教授。『ルポ資源大陸アフリカ 暴力が結ぶ貧困と繁栄』(東洋経済新報社と朝日文庫)で2010年の日本ジャーナリスト会議(JCJ)賞受賞。京都大学アフリカ地域研究資料センター特任教授を兼任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
60
この著者の『日本人のためのアフリカ入門』が面白かったので読んでみた。とても明快な口調、アフリカ生活歴が長い人ならではの生き生きしたレポート、そして「アフリカは自分で何かできる社会じゃなく、助けてやる対象」と考える日本の頭の古い企業経営陣への一撃など、中国の進出著しい現代アフリカと如何に付き合うべきかを、わかりやすく論じている。最低限本書に述べられたことぐらいは認識しておきたい。ただ、その中国や国連(日本の常任理事国入り問題も出てくる)との関連のせいか、やや「戦略的」な臭いも感じる。2019/08/26
きいち
32
アフリカ「から」見る視点が痛烈。◇立命館国際関係学部の、学生が国際社会のアクターになって交渉を行うゲーミングの授業おもしろいな。アフリカ各国を担当した著者の生徒たちが無関心をはねかえそうと能動的に行動していく、すばらしい。そしてたしかに、内向きなのは若者じゃない、大卒新卒男性中高年ばかりの経営層たちのほうがずっと内向き。いろいろ言い訳しながら、単に視点が限定されてるだけ。◇中国の存在感。ガチで対抗するんじゃなく、プラグマティックに戦略たてていくべき、と。我々がそれを知って評価していかねば実現しない。2020/04/19
スター
30
私自身もアフリカの事はよく知らないので、日本人のアフリカに対するステレオタイプに一石を投じる本著を興味深く読んだ。一部の日本人が思いたがっているより中国に対する評価が高かったり、電気自動車を開発した国があったり、援助より投資を希望する国も多いようだ。2025/08/15
hk
23
アメリカ人の5割超がアフリカを1つの国だと認識している。日本人は流石にそこまでではないが、アフリカに対する理解度はお世辞にも高いとは言えない。かくいうオイラもルワンダとウガンダがよくごっちゃになるm(__)m。まあ、あちらさんとしても日本人と中国人を見分けられまい、と高を括っていた。どっこい、本書はそんなステレオタイプを一刀両断にしていく。いわく「中国人はアフリカにおいて嫌われているという言説は右派の願望」。これはオイラも危ういと思料する。中国は印象操作でも狡猾だ。だからそんな初歩的なミスはするめいよ。2019/11/04
宇宙猫
21
★★ 2017年~2019年4月の連載をまとめたもの。今は中国の事もちょこちょこ報じられているし、アフリカ状勢は目まぐるしく変わるので一昔感がある。データが2014年までと結構古いし。アフリカ状勢は本当に生き物のようだ。新型コロナの流行で情報がますます伝わりにくくなっているし、今後がどうなるか心配な地域だ。2021/10/01
-

- 和書
- 新聖歌