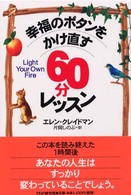内容説明
人と話をするときに、どういう言い方をするかということばかり、気にしていませんか?対話において本当に大事なことは、対話を通して伝えたいことは何か、ということです。そして、対話を通して何を伝えるのかということは、あなた自身にしか決められません。本書では、自分の「テーマ」を発見することから始めて、話題の決め方、他者とつながり他者を理解する方法、納得と合意の形成まで、生活や仕事における対話とあなた自身の“生きる目的”の関係についてわかりやすくお話ししていきます。
目次
第1章 今なぜ対話なのか(何のための対話なのか;自分を語る対話;対話のわかりやすさとは何か)
第2章 対話のためのテーマとは何か(人はテーマを持って自由になる;何について対話すればいいのか;「日本人は対話が下手」か)
第3章 対話をデザインする(どうしたら他者とつながれるのか―他者理解の方法;自分の言いたいことを明確に表現するには;対話による納得と合意)
第4章 対話することばの市民へ(この社会でしあわせに生きるために;個人が主体として生きる意味;対話することばの市民へ)
著者等紹介
細川英雄[ホソカワヒデオ]
1949年生まれ。早稲田大学名誉教授、博士(教育学)。専門は言語文化教育論。言語文化教育研究所八ヶ岳アカデメイアを主宰。1989年『パリの日本語教室から』でヨゼフ・ロゲンドルフ賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
57
ハウツーものというよりも哲学寄りの内容のように思った。漠然と考えていても、いざ話してみると頭から抜け落ちてしまうことは多々ある。そのあたりを平易にまとめている。2019/06/18
さこちゃん
16
内容について行けなかった。後半流し読み。2019/10/25
ほし
15
筆者は、対話の活動にはそれぞれがテーマを持つことが大切だと述べています。ここにおけるテーマとは、「生きる目的」を具体的に表したものを指しています。自分が何を大切にしているかに気づくことでテーマを見つけ、それを対話によって表現し、それぞれが納得、合意することで共同体が形成されていくとしています。 対話の方法論というよりは、対話とは何か、なぜ大切なのかという原論が述べられている本でした。(寧ろ筆者は方法論に否定的です) 自分も対話とテーマを意識して、社会との繋がりを実感しながら生きていきたいと思いました。2019/08/26
Ryo
14
対話という言葉は誤解されて居るように思う。自分も少し前まではただ話し合うという事の言い換え程度に思っていた。「対話」が弁証法的な匂いを持った、相互理解に基づいた創造活動の要素を持つものだと知ったのはつい最近の事だ。この本では「対話」というものが平易に説明されて居る。人とは本質的に相対的な存在であり、他者との関係性無くしてアイデンティティを所持し得ない。そして、人と相対的である為には、他者を代えの効かない独自の存在であると認め、フラットな立場である必要があり、そこに勝ち負けを存在させてはいけない。2019/07/11
森
11
年末図書館で借りました。単なるハウツー本ではなく、さらに川上の議論もされており、内容が深いです、良い本です。暇な時に購入して熟読予定です。2020/01/05
-

- 電子書籍
- 闇金ウシジマくん外伝 滑皮組ヤクザメシ…
-

- 洋書
- Das äuße…