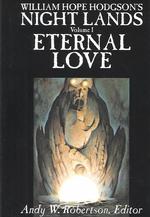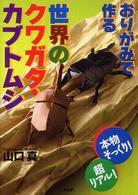出版社内容情報
科学的手法の進展により新発見の続く考古学。その最先端をわかりやすく伝えるとともに、通説に対して挑戦的な研究をも多数紹介する。
内容説明
科学的な手法の発達によって、近年、考古学の成果が多数挙がり、考古学の年表は全面的に書き換えられつつある。旧石器捏造事件で考古学の危うさが指摘されて以来、科学的な確からしさが常に問われている。そこで実証的な考古学の最新成果を一般の読者にわかりやすく伝えるとともに、通説をそのままなぞるような水準にとどまらない、挑戦的な研究を紹介。旧石器時代から古墳時代までの全貌がわかるだけでなく、考古学ファンの批判に耐え、知的好奇心を満たす最前線の研究案内。
目次
1 旧石器・縄文時代(列島旧石器文化からみた現生人類の交流;縄文時代に農耕はあったのか;土偶とは何か;アイヌ文化と縄文文化に関係はあるか)
2 弥生時代(弥生文化はいつ始まったのか;弥生時代の世界観;青銅器のまつりとはなにか;玉から弥生・古墳時代を考える;鉄から弥生・古墳時代を考える)
3 古墳時代(鏡から古墳時代社会を考える;海をめぐる世界/船と港;出雲と日本海交流;騎馬民族論の行方;前方後円墳はなぜ巨大化したのか)
著者等紹介
北條芳隆[ホウジョウヨシタカ]
1960年長野県生まれ。岡山大学法文学部卒業。広島大学大学院文学研究科博士前期課程修了。大阪大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。現在、東海大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
niwanoagata
terve
kk
さとうしん