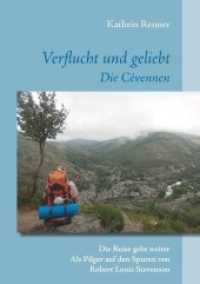出版社内容情報
いま政治学では何が問題になっているのか。政治史・政治理論・国際政治・福祉・行政学・地方自治などの専門研究者が12のテーマで初学者を導く政治学への道案内。
内容説明
初学者から学べる現代政治学への道案内。
目次
1 日本と世界(日本政治 議院内閣制と政党政治―日本はいかなる政治システムの国か?;行政学 公務員制度批判について考えよう;地方自治 権限と財源から見た地方自治 ほか)
2 歴史と思想(政治理論 官僚制の思想史―デモクラシーの友か敵か?;西洋政治思想史 敗戦の経験とデモクラシー―戦後日本の一つの思想的伝統;日本政治外交史 戦後日本外交入門―日中国交正常化を事例に ほか)
3 比較と地域(比較福祉政治 生活保障システムを比較する;アメリカ政治 政治不信の高まりと政治的分極化;ヨーロッパ政治 変貌するドイツ政治 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
樋口佳之
31
封建制の再現を求める儒家の思想は、最初から決定的に時代遅れだった。しかし、最初から時代遅れの思想は、何があっても古びることはない。最初から古いのだから。だからこそ、儒教・儒学は政治思想として力を持ち続けた/ふむふむふむ。著作全体からは脱線気味ですが。2021/04/06
やまやま
17
政治学に向かう視点のいくつかを提示している編集は教科書代わりに有用であろう。各国の政治を議論する際に議会の構造の知識は重要であるという点や、公務員制度についての議論は行政法・行政学からの展開がなされた後に、官僚制の歴史につながる展開である。行政という意味では地方自治も重要であるが、著者が財政学の方で、内容的に派手さのない議論がなされている。思想と歴史のところは久しぶりに小田実の戦敗国ナショナリズムを拝読し、また日中国交正常化における周恩来の「言必信、行必果」も回想に難はなかった。よくまとまっています。2021/05/02
seki
16
大学の先生がそれぞれの専門の小論をまとめたものといった感じ。決して悪い内容ではないのだが、タイトルにある「教養」「入門」といったキーワードに惹かれて、手にとってみたところ、あまりに内容が硬すぎ、面白みもないので、やや期待外れだった。しかし、広く、政治や行政のことを少し知りたいという人にはおすすめ。興味ある分野があれば、そこを掘り下げた本をまた見つけてみるのがいいかも。2019/12/06
かんがく
13
安倍晋三首相の出身学部が「政治学入門」を出すというのも面白いなと思って手に取ったが、それぞれの章の著者の専門分野について簡単に述べられているだけで、内容の特色は薄かった。参考文献に挙げられていた本に手を出してみようと思う。2019/04/14
さとうしん
12
成蹊大学法学部政治学科の教員が各自の研究内容を一般向けに解説したものだが、第6章「戦争の経験とデモクラシー」や第8章「ロシアにおける第二次世界大戦の記憶と国民意識」など、「こういうのも政治学に入るのか」と、政治学の幅広さが感じられる内容になっている。政治学について学ぶというより、政治学の中で自分が興味を持てる研究を探るという方向での入門書。2019/04/08
-

- 洋書電子書籍
- The Human Hypothala…