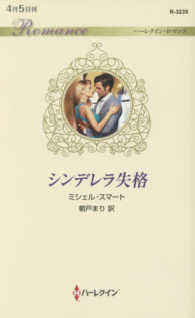出版社内容情報
自由な個人から大衆社会への転換を、人間・国家・意識・政治・道徳・思考の六つの領域で考察。不安定化する人類文明の行く末を探る。
船木 亨[フナキ トオル]
著・文・その他
内容説明
「自由で平等な個人」という近代にあった理想。だが、明らかにそれは誤りである。ポピュリズムが跋扈するポスト・トゥルースの現代は、「群れ」社会への転換をすでに遂げている。その転換も昨今急激に生じたのではない。現代思想で論じられてきたその社会の変容を、順に「人間」「国家」「意識」「政治」「道徳」「思考」の六つの主題について解き明かしていく。AIで人間が不要になる、といった皮相な議論よりもはるかに深い次元で人間の終焉を考察し、混迷する人類文明の行く末と、これからの生き方について講義する。
目次
プロローグ 近未来に待ち受ける生活とは?
第1章 人間―家族は消滅しつつある
第2章 国家―社会は国家ではない
第3章 意識―自我は存在しない
第4章 政治―ヒトはオオカミの群れの夢を見る
第5章 道徳―群れの分子には身体のマナーがある
第6章 思考―統計と確率のあいだで決断せよ
エピローグ 近代の発想を頭からすべて洗い流そう!
著者等紹介
船木亨[フナキトオル]
1952年東京都生まれ。東京大博士(文学)。東京大学大学院人文科学研究科(倫理学専攻)博士課程修了。専修大学文学部哲学科教授、放送大学客員教授。専攻はフランス現代哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
武井 康則
oooともろー
肉尊
みかづきも🍀