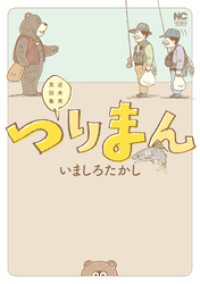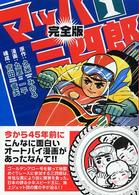出版社内容情報
万葉集全体を歴史学・民俗学・考古学の視点も駆使しながら解剖し、最古の歌集が伝える古代史、文化史をさぐっていく野心的な入門書。
上野 誠[ウエノ マコト]
内容説明
歴史の中の『万葉集』。歌の拡がりを示す、出土した考古資料。民俗学が教えてくれる歌の文化の本質。それらを総合することによって、『万葉集』の新しい読み方を提案する画期的な書。“情感を伝える歌”“事実を伝える日記”“共同体が伝える物語”。古代人は、どうやったら、これらをうまく書き表し、後世に残せると考えたのか。斬新な古代文化論、万葉文化論が、ここに出現。
目次
第1章 歌と文字との出逢い
第2章 歌を未来に伝える意志
第3章 歌の作り手と歌い手
第4章 木簡に書かれた歌
第5章 日本語を漢字で書く工夫
第6章 日本型知識人の誕生
第7章 日本型知識人と神々
第8章 消えゆく物語をどう残すか
第9章 日記が芸術になる時
著者等紹介
上野誠[ウエノマコト]
1960年、福岡県生まれ。国学院大学大学院文学研究科博士課程後期単位取得満期退学。博士(文学)。現在、奈良大学文学部教授(国文学科)。研究テーマは万葉挽歌の史的研究、万葉文化論。日本民俗学会研究奨励賞、上代文学会賞、角川財団学芸賞を受賞。歴史学や考古学、民俗学を取り入れた万葉研究で、学会に新風を送っている。著書多数。オペラや朗読劇の脚本も手がける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なお
45
『万葉集』は八世紀に成立した最古の歌集。二十巻からなり四五一六首の歌が収められている。古代の人々にとって、歌は他者とのコミュニケーションのための大切な道具。その時々の心情が綴られた歌を知る事は、古代の人々の心を知る事でもある。八世紀には日本語を記すための日本語固有の文字がまだなく、『万葉集』は訓(漢字の意味を日本語にあてる)や万葉仮名(漢字の意味を離れて、音のみを日本語にあてる)が用いられ、全て漢字で書かれている。中国を中心とした漢字文化圏の辺境である事が、とらわれなく融合されて独自の文化を創ったという。2024/07/21
獺祭魚の食客@鯨鯢
22
映画「君の名は」のモチーフは万葉集の歌に記されている「誰そ彼」「黄昏」夕暮れの薄暗がりで「あなたは誰?」と言わないでと訴えかける女性の歌です。映画だけでなく、4516首の古代の歌集が1000年以上の時空を超えて21世紀の私たちの心情に響くのは、まだまだ日本人は「やまとごころ」を失っていない証拠でしょう。富士山や桜、四季の移ろいを愛でる気持ちは外国人に指摘されるまでもなく日本人に生まれてきてよかったと思える瞬間ですね。作者は万葉集を「声の缶詰」としました。缶を開けると「いにしえの空気」が味わえるからですね。2017/10/28
やいっち
20
「万葉集」論としても、ユニークな視点が幾つも。ただ、内容からする、続々と出土した木簡などの考古資料や民俗学の新しい知見から読み解く「古事記」や「万葉集」あるいは「歌」という趣向だったような。明日、ブログに感想文をアップします。2017/08/14
りー
12
挑戦的な万葉集論でした。特に、親しんできた山上憶良の「瓜はめば」「しろがねも」の一連の歌が、ことばがきから続けて読むと、仏教を“意図的に歪曲”していると解釈できる、という指摘に、あっ!と思いました。全ての執着を棄てる仏教の教えが日本で変化する。鎌倉仏教・・・親鸞へ繋がる片鱗が既に万葉集で見られるとは!それが可能だったのは「辺境、周辺であるがゆえに、その後のユーラシア大陸における大きな言語の変化の波が届きにくく、むしろ古層の言語が優勢のまま残った」日本語の位置故である、というのも面白かったです。2018/10/01
y_nagaura
12
日本語とは何か。歌とは何か。日本人としてのアイデンティティに関わるテーマが、万葉集を軸として語られていく。 日本語と漢字の関係性や、比較言語学からみた日本語、貴族の処世術として生まれた日記など、日本独自の文化の根幹をなす慣習がいかに生まれたかが分かり、目から鱗でした。日本型知識人の原型という山上憶良による、ある種詭弁のような語り口も、とても示唆的。 万葉集は「言葉の文化財」という著者の言葉の重みを感じられ、日本語がますます好きになりました。2018/07/15