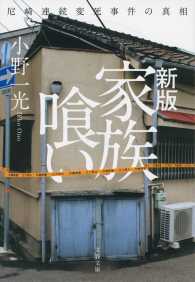出版社内容情報
地方自治の原理と歴史、人口減少やコミュニティ、憲法問題など現在の課題を解説。市民が自治体を使いこなすための地方自治入門講義。
今井 照[イマイ アキラ]
内容説明
一九四七年五月三日、日本国憲法が施行された日に地方自治法も施行された。それは偶然ではない。憲法の施行には、地方自治法の施行が欠かせなかったのだ。それから七〇年。地方自治や地方分権は当たり前の考え方になったが、果たして自治体は私たちのものになったのか。人口減少やコミュニティ、憲法問題なども交え、地方自治のしくみや原理、歴史、現在の課題をわかりやすく解説。深いところから基礎を知り、自治体を使いこなしたい市民のための、これまでにない地方自治入門講義。
目次
第1講 自治体には三つの顔がある
第2講 地方自治の原理と歴史
第3講 公共政策と行政改革
第4講 地域社会と市民参加
第5講 憲法と地方自治
第6講 縮小社会の中の自治体
著者等紹介
今井照[イマイアキラ]
1953年生まれ。専門は自治体政策。福島大学行政政策学類教授。東京大学文学部社会学専修課程卒業。東京都教育委員会、東京都大田区役所勤務を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みっくん
31
地方自治を住民の手に。それを実現するための地方自治の講義本。地方自治の歴史から、抱える問題、地方創生まで網羅。考える人は考えるし、考えない人は考えない。でも、関係ない人はいないかな。。。2017/02/26
おさむ
28
消滅可能性自治体などと不安を煽る提言をした元総務大臣もいるが、この本の方が建設的。人口減少は地方からの都市への流入ではなく、東京圏の人口の固定化をもたらし、日本全体の活力低下につながると指摘します。また、平成の大合併では財務の改善というお題目で自治体は半減して1800弱になったが、実際には何も改善せず、住民が割りを食っただけの「大失敗」だったと批判します。先進国の基準で見ると、日本の基礎自治体の規模は異常なまでに大きいという指摘は初耳でした。なんでも大きいことは良いことだ、という思想からの脱却が必要です。2018/07/30
大先生
9
元公務員の福島大学教授による地方自治の入門書です。入門書とはいえ、地方自治のしくみや原理、歴史、現代の課題、憲法問題等について深いところから解説されており、やや難しい部分もあります。国策としての「地方創生」に関する批判は鋭いですね。①「創生」って何もないところから作り出すという意味で、明らかに東京目線の言葉であるとか、②地方創生人材支援制度なんてつくって国家公務員を自治体に出向させられるようにしているけど、誰のための地方創生なのか?国が自治体を支配しやすくするための道具ではないか?等など。勉強になりました2023/01/12
かばお
6
この本、すごくおもしろい。タイトル通り、講義形式で地方自治について書いてある。地方自治の制度論がメインで、それらの裏側にある国の思惑や歴史的沿革の解説も押さえていて、地方自治の知識をコンパクトに得られる新書と呼ぶにふさわしい本だな。地方自治法の勉強に関する前提知識を得る目的で読んだが、これはお釣りが来る。個人的には、第5講の内容が興味深い。「地方自治の本旨」の循環論理や町村議会の違憲性の指摘はなるほど、と考えさせられた。2017/06/25
もけうに
5
お堅い書名に反して、物凄く面白かった。極めて丁寧且つ真面目に書かれているが、例えがわかりやすいので非常に理解しやすい。「地方創生」を扱うそこらの新書とは一線を画すしっかりした内容。地方自治の考え方・歴史・システムがよくわかり、目から鱗。税金はまず国の財布に入れ、都道府県→市町村の箱に移していく、という説明が非常にわかりやすい。地方から東京圏への移動は大学進学時・就職時に集中しており、それも年々減少している。経済的に移動できなくなり、人は動かなくなった。東京一極集中は、人口ではなく政治・経済・文化。2025/03/09
-
![春嵐(上) 風烈廻り与力・青柳剣一郎[18] 祥伝社文庫](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0577202.jpg)
- 電子書籍
- 春嵐(上) 風烈廻り与力・青柳剣一郎[…
-
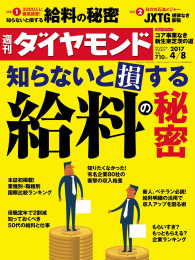
- 電子書籍
- 週刊ダイヤモンド 17年4月8日号 週…