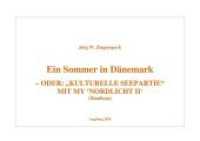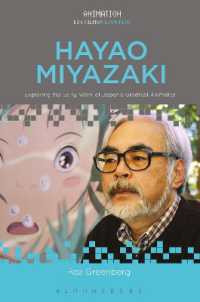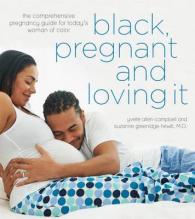出版社内容情報
自分の直観と経験だけで人を動かすのには限界がある。マネジメントの基礎理論を学べば、誰でもいい上司になれる。人事のプロが教える、やる気を持続させるコツ。
海老原 嗣生[エビハラ ツグオ]
内容説明
自分の直感と経験だけで組織と人を動かそうとするには、限界がある。マネジメントの基礎知識を学べば、誰でも一定レベルの上司になれるのだ。「雇用のカリスマ」である著者が、クイズ形式でわかりやすく解説する「2W2R」とはWhatとWay、ReasonとRange。何を、どうやって、なぜ、どこまでを決めてあげること。「三つのギリギリ」とは、(1)易しすぎず難しすぎず、できるかできないかの線を提示する。(2)活かし場を用意する。(3)逃げ場をなくす。というギリギリの目標を用意すること。
目次
はじめに 「あの人はすごい」―その理由は、マネジメント理論でけっこう説明できます。
第1章 なぜ、企業は社員のやる気を大切にするのか
第2章 やる気の源泉=「機会」と「支援」の鉄則
第3章 やる気を絶やさないための秘訣
第4章 もう一つのR(=Range)は、なぜ「スーパーな力」なのか
第5章 世界でも特殊な日本型のキャリア構造
第6章 学んだことを人に教え、自分でも実践する
あとがき リクルートの「元気とやる気」の秘密を、みなさんに
著者等紹介
海老原嗣生[エビハラツグオ]
雇用ジャーナリスト。1964年生まれ。20年以上、雇用に関する取材、研究、提言をおこなう。リクルートキャリア社の第1号フェロー“特別研究員”として同社発行の人事・経営誌『HRmics』の編集長を務める。立命館大学経営学部客員教授。奈良県人材・組織マネジメント部会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
アナクマ
アナクマ
チェアー
ともふく
O. M.