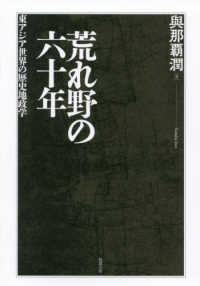出版社内容情報
今日の政治体制は、近代政治哲学が構想したものだ。ならば、その基本概念を検討すれば、いま我々の体制が抱える欠点についても把握できるはず! 渾身の書下し。
内容説明
我々がいま生きているこの政治体制は、近代の政治哲学が構想したものだ。ならば、政治哲学やその概念を検討すれば、今日の民主主義体制の問題点についても、どこがどうおかしいのか理論的に把握できるはずだ!人間が集団で生きていくための条件とは何か?“主権”の概念が政治哲学の中心におかれる中で、見落とされたのは何だったのか?近代前史としての封建国家を出発点に、近代の夜明けから、その先鋭化・完成・自己批判に至るまで。ホッブズ・スピノザ・ルソー・ヒューム・カントの順に、基本の概念を明快に追っていく。
目次
第1章 近代政治哲学の原点―封建国家、ジャン・ボダン
第2章 近代政治哲学の夜明け―ホッブズ
第3章 近代政治哲学の先鋭化―スピノザ
第4章 近代政治哲学の建前―ジョン・ロック
第5章 近代政治哲学の完成―ジャン=ジャック・ルソー
第6章 近代政治哲学への批判―ヒューム
第7章 近代政治哲学と歴史―カント
結論に代えて―近代政治哲学における自然・主権・行政
著者等紹介
國分功一郎[コクブンコウイチロウ]
1974年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。現在、高崎経済大学経済学部准教授。専攻は哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
chanvesa
44
わかりやすい授業を受けているかのよう。ただし前期が終わり、後期の授業も受けたい、もう少し現代政治思想の話も聞きたいと思わせる。その授業はヴェーバーから始まるのかもしれない。近代政治哲学の三権分立や主権の議論が進展していく中で、行政と立法の問題は、解決してないどころか、それこそヴェーバーの官僚制の背景にある行政の拡大化として、未だ大きな問題として存在している。東京都知事のスキャンダルにしても、あと数日で都議会が閉会という状況で、都政に混乱をもたらしたという言葉の「混乱」とはなにかを考えなくてならない。2016/06/19
ゆう。
40
近代の哲学者たちが、人間の本質を考察しつつ、民主主義と主権、統治のあり方を示してきたのか、歴史的に述べられている。現代を生きる私たちにとって、数の原理だけで民主主義という政治暴力がなりたっているからこそ、学ぶべきことは多いように感じた。真の民主主義や国民主権を実現させるためにも。2020/01/16
ta_chanko
38
ホッブズ・ロック・ルソーの自然状態の定義は、実はそれぞれ異なっている。もっとも原始的な状態を仮定したのがルソー。他者との関係性が発生している状態を定義したのがホッブズ。そして所有権や家族制度が確立している状態を自然状態と考えたのがロック。凄惨な宗教戦争が終わり、領域が曖昧な封建国家の時代から、領域・構成員ともに明確な国民国家への移行期に考案された近代政治哲学。ルソーの一般意志とは、憲法のようなものか。法律は一般的、行政は個別的。必然的に行政権が大きな力を持ちやすくなる。それをいかに抑制するかが大切。2023/09/06
sayan
37
機内で読了。著者の作品は「暇と退屈の倫理学」で独特の視点に面白さを覚え、今回の著書を手に取った。「自然権」は権利ではない、など独特に視点に若干戸惑いを覚えるも、リズミカルな文体で読みやすかった。なかでも、p.43でホッブスに言及しながら「能力の平等」から「希望の平等」を指摘、そして平等が戦争をうむ、など興味深かった。また、目から鱗だったのは、p.143-144の自己愛と利己愛の違いを明快な文章で示されている箇所。それは、絶対と比較評価という軸が意味合いとして抽出でき非常に興味深かった。2017/05/06
おせきはん
31
ホッブス、ルソー、カントらが論じてきたことがわかりやすく解説されています。行政が巨大な力を持つようになる中、法による支配でどこまで歯止めをかけられるか、現代政治における重要な論点を考えるうえで大いに参考になりました。2025/02/12
-
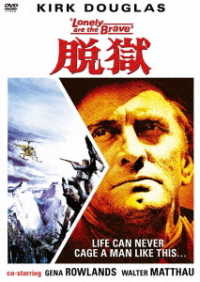
- DVD
- 脱獄(スペシャル・プライス)