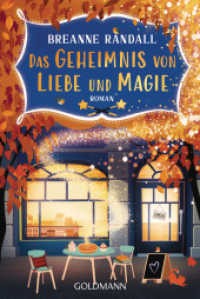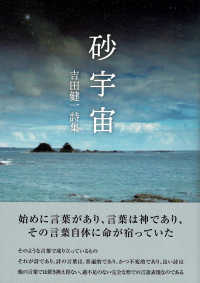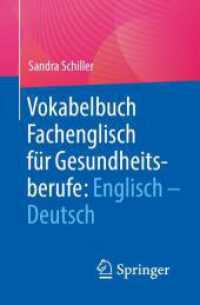出版社内容情報
行き詰まり、悶々とした状況にある日本社会の見取図を描き直し、教育・仕事・家族の各領域が抱える問題を分析、解決策を考える。
内容説明
高度経済成長、バブルは遠い彼方。問題が山積みの日本社会には、悶々とした気分が立ちこめ、「もつれ」+「こじれ」=「もじれ」の状況にある。この行き詰った状況を変えるには、一体どうしたらよいのか?「教育」「仕事」「家族」それぞれが抱える問題について考え、解決策を探る。言葉を紡ぐ一冊。
目次
第1章 社会の「悲惨」と「希望」(「悲惨」について;「希望」の現場より)
第2章 戦後日本型循環モデルの終焉(格闘する思想;激動する社会の中に生きる若者と仕事、教育)
第3章 若者と雇用(若者にとって働くことはいかなる意味をもっているのか―「能力発揮」という呪縛;若者と雇用をめぐる現状―何が求められているのか)
第4章 教育のアポリア(普通科高校における“教育の職業的意義”のあり方;専門高校の意義を再発見する;いじめ・体罰・自殺の社会的土壌)
第5章 母親・家族への圧力(いま、家庭教育を救うには;不安の中で先祖返りする若者たち―「夫は外、妻は家庭」意識の増加;親としてのあり方;「人間力」の圧力―女性たちは何を求められているのか?)
著者等紹介
本田由紀[ホンダユキ]
1964年生まれ。東京大学大学院教育学研究科教授。専門は教育社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とよぽん
30
タイトルは「もつれ、こじれる」を合体させたものという。「不安の中で先祖返りする若者たち」という見出しの章が気になり、そこを中心に読んだ。雇用が不安定で、結婚や子育てにも不安を抱く若者たち・・・そのため「夫は外、妻は家庭」という性別分業志向の増加に転じたのだという。でも、それでは問題解決にはならないと思う。著者も、働き方の見直しや子育ての社会化といった政策が必要だと述べている。教育や経済の格差が人々の分断をさらに拡大している今、このままでは、女性が輝いて活躍する社会なんて絵に描いた餅だ。永遠に。2019/06/06
ゆう。
25
本著は、『軋む社会』の続編だと著者は位置づけています。教育、仕事、家庭と著者が戦後日本型循環モデルとあらわしている状況が、新自由主義的構造改革によって崩されているなかで、著者なりの新しいモデルを提示しています。それは、教育、仕事、家庭と一方通行的なモデルであった日本型循環モデルを、双方向型に変革することだとしています。しかし、仕事(労働)についてはジョブ型正社員を肯定的に受け止め、キャリア形成のなかに組み入れていることには注視する必要があると思います。著者らしい歯切れの良い切り口でした。 2015/01/24
ステビア
24
納得できるところもあるのだがこの人の根底にあるのはmediocre left mentalityだということを確信した2021/10/04
1.3manen
24
悲惨でない者から悲惨な者に向けられる憎悪は、その反作用として後者から前者への憎悪をも生み出す(020頁)。図3戦後日本型循環モデルの破綻(073頁)で、離学後に低賃金で不安定な仕事に就かざるを得ない層の拡大が気になる。非正社員層が厚くなり、中核的正社員が彼らに取り巻かれる構造。能力は、必然的に、個々人の人格や本質とは切り離されて可動化され、個人の外側からの働きかけを通じた形成や評価が可能ものとみなされなければならない(123頁)。2014/11/21
しょうじ@創作「熾火」執筆中。
21
【15/11/22】教育社会学者である本田氏は、種々の統計資料を丹念に読み解き、その指標の不備を指摘しつつ、「戦後日本型循環モデル」のほころびについて論及している。注目したいのは、専門高校に対する相対的に高い評価であり、「柔軟な専門性」が提供されることで、社会に飲み込まれないようにする立脚点としている点である。ないものねだりを承知で言えば、マックジョブや3K・5Kに象徴されるような仕事を誰が担うのかについての言及が欲しかったと思う。2015/11/22