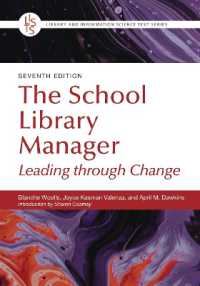内容説明
怒る、悦ぶ、悲しむ、妬む…。生きていれば、さまざまな「感情」が誰の心にも去来する。だが、その本質は何か。プラトンからアーレントにいたる歴史の糸を辿り、西洋では伝統的に「理性の敵」として語られることが多かった感情に対し、新しい視点から照明を当てる。古代ギリシアに始まり、デカルト、スピノザ、マルブランシュなどを経て今日にいたる感情をめぐる哲学的言説の系譜を整理し、それぞれの細部を精神史の文脈に置きなおす。哲学史の新たな読みを果敢に試みる感情の存在論。
目次
序章 感情の問題とは何の問題か
第1章 感情の哲学、あるいは驚きと悦びについて
幕間 感情の分類、あるいはストア主義について
第2章 感情の科学、あるいは情動主義について
幕間 感情の受動性、あるいは機械論的決定論について
第3章 感情の伝達、あるいは公共性への意志について
著者等紹介
清水真木[シミズマキ]
1968年生まれ。明治大学商学部教授。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。哲学、哲学史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
27
感情とは、思考と懐疑への道として、 根源的な真理への道として把握され 吟味されねばならない(016頁)。 キケロが感情の分類に当たり最初に設定するのは、 欲望、悦び、不安、苦悩(117頁)。 感情の科学とは、感情に関する通俗的な 見方を前提として、これを精密に記述 しなおす作業のモデル(162頁~)。 ストア主義の生活の理想は、アパテイアー。 感情からの自由(204頁)。 明日は、スピノザ『エチカ』に挑みたい。 2014/08/02
きいち
21
例えば尖閣でも靖国でもだけど、問題をこじらせてるのは「貶められてる」という感情の問題、それは向こう側もそうだし、オヤジ向けの週刊誌の中吊りに踊る言葉の通りこちら側も同じ。そんな状況をうざいと感じた時、個人としてどう振る舞えばいいのかヒントになるかも、と手をのばした。◇この本の戦略は、心理の問題ではなく哲学の問題として、とにかく引いて見ること。デカルト、ヒューム、カント、アーレント、冒頭の芸術作品への感動の話から、感情のブラックボックス化に徹頭徹尾抗っていく。直接はよう使わんけど、勇気をもらえる一冊だった。2014/07/27
masabi
15
感情とは何かという問題に哲学で立ち向かう。感情は世界と自身との在り方を決め、さらに自分自身を照らす。プラトンは超人的なもの、ストア派と以後の哲学者は理性の敵、アーレントは公共性の意志として感情を捉えた。2014/08/15
ハイちん
14
「感情が価値判断の先に立つ」という立場を情動主義という。「何となく」の感情によって「好き・嫌い」といった価値判断がされるというこの立場に立てば、あらゆる価値は「何となく」決まっていることになり、またあらゆる感情も「何となく」感じているということになる。読んで、なるほど僕は情動主義者だったんだと思った。価値に価値を見いだせない情動主義者が抱える空虚さも指摘してあってギクッとした。なんで情動主義者になったんだろう。たぶん伊藤計劃とかファイトクラブの影響のような気がする(両方大好きだが)。自覚できて良かった。2018/11/25
さえきかずひこ
10
プラトンの驚きに始まる哲学史における「感情への問を正しく仕上げ「感情とは何か」という問によって本当に問われるべきものが」(P.248)晩年のアーレントによるカント『判断力批判』の解釈にあることを論じる第3章が読みどころ。「アーレントの理解に従うなら」「感情は、単なる内面的、個人的、私的な現象なのではなく」「他人からの承認を想定して何らかの仕方で言葉へと置き換えられるプロセスが必要なのです」「私の感情は、その都度あらかじめある特別な仕方で普遍性を具えていると考えなければならないことになります」(P.242)2019/10/30