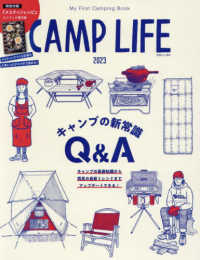出版社内容情報
中国とは何か? その原理を解く鍵は、近代史に隠されている。グローバル経済の奔流が渦巻きはじめた時代から、激動の歴史を構造的にとらえなおす。
内容説明
中国とは何か。その原理を理解するための鍵は、近代史に隠されている。この時代に、「幇」とよばれる中国団体をはじめ、貨幣システム・財政制度・市場秩序など、中国固有の構造がつくられたからだ。本書は経済史の視座から一六世紀以降の中国を俯瞰し、その見取り図を明快に描く。かつて世界に先んじた中華帝国は、なぜ近代化に遅れたのか。現代中国の矛盾はどこに由来するのか。グローバル経済の奔流が渦巻きはじめた時代から、激動の歴史を構造的にとらえなおす。
目次
プロローグ―中国経済と近代中国史
1 ステージ―環境と経済
2 アクター―社会の編成
3 パファーマンス―明清時代と伝統経済
4 モダニゼーション―国民経済へ向かって
エピローグ―中国革命とは何だったのか
著者等紹介
岡本隆司[オカモトタカシ]
1965年生まれ。現在、京都府立大学文学部准教授。著書に『近代中国と海関』『属国と自主のあいだ』(いずれも名古屋大学出版会、前者で大平正芳記念賞、後者でサントリー学芸賞を受賞)、などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
59
再読。最近香港問題が騒がしい昨今、江南を中心とした商業の発展に興味が湧いて読む。前回読んだ時には中国独自の権力構造やそれによる上下二極化が特に目についたが、今回は明のイデオロギーと結びついた現物主義や対するアンチテーゼとしての清の商業などに特に興味を惹かれつつ読む。あと本来の目的として序で触れられている河北と江南の発展の違いやそれに結びついた人口形態もかな。やはり中国史として読むには向いていないけど、現在の中国の権力構造や経済活動が当時と切り離せない部分があると教えられ、そういう意味では本書は史だと思う。2020/07/23
HANA
38
明から日中戦争までの社会制度と経済活動を解説した一冊。近代中国の通史かと思って買ったのだが、そういう意味では看板に偽りありかな。ただこれが、単なる通史よりよほど面白いのである。ここでは中国独自の権力のあり方や上と下との社会の二分構造が明らかにされており、これを読むと最近話題のシャドーバンキングは目新しいものではなく、前近代より脈々と受け継がれてきたものではないかという気もしてくる。他にも中央集権化に失敗した理由や近代の西洋との経済を通じた関わり合い等、読むもの全てが目新しい話題ばかりであった。2013/07/26
Miyoshi Hirotaka
35
国内統一後の勢力拡大は近代化の法則。フランス革命後のナポレオン戦争や南北戦争後の米国の太平洋進出もその例。これを中国に当てはめると、共産党の国内統一により、秘密結社や軍閥が一掃され、党、国家という政府権力が誕生。冷戦構造の中で世界経済との関係が希薄になったことにより、物資や金融面での統制が強化された。文化大革命後に改革開放路線へと舵を切ったが、政治権力が及びにくい明・清以来の伝統的社会構造との格差、分断が顕在化し、国内一体化が危うくなった。経済成長のスローダウンはそれが重大な局面になりつつあることの証だ。2015/03/29
姉勤
32
モノとカネの流れを通して漢代〜現代まで続くチャイナの特殊性を説く。戦乱と異民族の侵入により支配者が何度も替わった中国は、本来国家が保証すべき治安と経済を担保できず(する気もなく)、自給自足できる大小の集団と、それを統べるリーダーを認定し、彼らの上前をはねる(徴税)ことを「統治」と呼んだ。ヤクザな社会だが、そのヤクザなネゴシエートや利への聡さが現在の共産党王朝まで綿々と続いている。国家を一体の生物と例えるならば、普段はバラバラな群体が時にキノコを形作る菌類のような集合体。中国とのトップ会談は意味をなさない。2016/10/15
Y
23
読む前に近代中国史というタイトルから連想していたものとはだいぶ異なっており、経済という観点を中心に中国社会を論じている。権力と民衆の関係について、また現代の中国を見ていて疑問に感じることは今に始まった話ではなくて、根深いものなのだということがよくわかった。2013/08/29
-
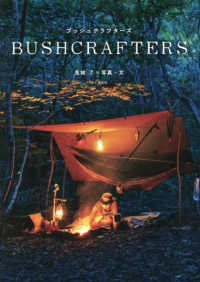
- 和書
- ブッシュクラフターズ