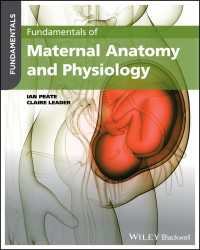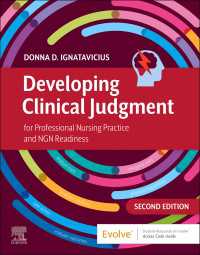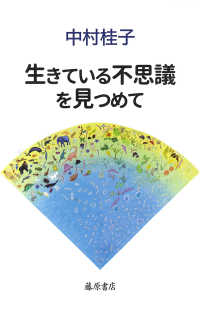出版社内容情報
ヒトはいかにしてヒトになったのか? 道具・言語の使用、文化・社会の形成のきっかけは狩猟採集時代にあった。人間の本質を知るための進化をめぐる冒険の書。
内容説明
チンパンジーと共通の祖先から分かれておよそ六〇〇万年。この六〇〇万年という時間をかけて、私たちヒトは進化を遂げた。進化したのは身体的な特徴に限ったことではない。ヒトの「心」の特性や能力も、環境に適応するなかで、とりわけ狩猟採集生活を送るなかで進化した。それは、普段、なにげなく行なっている行為や行動のなかに見てとることができる。なにが私たちヒトをヒトたらしめているのか、なにが私たちの特徴なのか、これらの問題に「心」の進化の視点から迫る。
目次
第1部 ヒトをヒトたらしめているもの―ヒトの6大特徴(600万年前―分岐点;すべては直立二足歩行から;ホモ・モビリタス―すべての大陸へ ほか)
第2部 狩猟採集生活が生んだもの―家畜、スポーツと分業(狩猟採集民としてのヒト;動物を飼いならす;ヒトのよき相棒―イヌ ほか)
第3部 ヒトの間で生きる―ことば、心の理論とヒトの社会(おとなになるまでの長い時間;ホモ・ソシアリス―ヒトの社会;顔の記憶 ほか)
著者等紹介
鈴木光太郎[スズキコウタロウ]
1954年宮城県生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退。現在、新潟大学人文学部教授。専門は実験心理学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
シュラフ
30
人間はヒトという動物である。ヒトは約600万年にチンパンジーと共通祖先が枝分かれした。その後、何百~何千~何万の世代を繰り返すことを通じてヒトは進化して今の姿となった。ヒトをヒトたらしてめているのは、「心の理論」(相手の心を推察するもの)なるものを持つことで、チンパンジーとは異なり、ヒトは社会や社会性とかいうものを作り上げたこと。しかしながら、ヒトはこの「心の理論」を持ったがゆえに社会的動物となり、人間の心には葛藤というものがうまれてしまった。漱石の『こころ』の葛藤の世界も、人間の進化の結果といえようか。2017/08/19
ta_chanko
24
ホモ=サピエンス(賢い人)とは何者なのかを、多角的な視野から考察。ホモ=モビリタス(移動する人)、ホモ=リデンス(笑う人)、ホモ=ルーデンス(遊ぶ人)ホモ=イミタトゥス(真似する人)...。直立二足歩行、火の使用、道具の製作と使用、調理、言語の使用、文字の使用、農耕と牧畜、遊び(スポーツ・芸術)、宗教、虚構の共有...。進化の過程を辿りながら、ヒトがどのようにして共有できる「心」を獲得していったのかがよく分かった。男女の分業による性差の拡大も興味深い。特に「投げる」能力の差が大きい! 2024/04/30
びっぐすとん
18
再読。ヒトの進化というと人類学者の領域と思うが、心理学の分野からヒトが他の動物と何がどう違うのかを説明。他の動物とは桁違いに大きな脳がもたらしたヒトの特技は数あるが、他者の気持ちを察したり、神や未来を空想する力、言葉を用いたコミュニケーションなど「心の理論」がヒトをヒトたらしめるというのは分かりやすい。ヒトには当たり前過ぎて特別とも思わないことが、実は他の動物には出来ない。「ココロ」を持つのはヒトだけ。SFでアンドロイドとの違いもそこに行着くし、脳という器の進化だといわれると「ココロ」は複雑に思っちゃう。2020/06/14
うえ
9
マジか。「火を指す名詞は、日本語の火のように、頭が「はひふへほ」で始まる。私の知る外国語では、中国語でフォ、朝鮮語でプル、英語でfire、フランス語でfeu、スペイン語でfuego、ドイツ語でfeuerである。これは火や炎を吹く際のその音に由来するからなのだろう。ほとんどの単語は(音と意味されるものの間に必然的関係はない)が火の場合は必ずしもそうは言えないことになる。火の調節はフルートや笛とも無関係ではない。火吹き筒など…フルートや笛のようにも見える。笛は、古いものでは3万6千年前の遺跡から出土している」2016/11/20
おしげ
4
読了2013/12/06