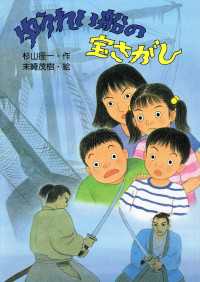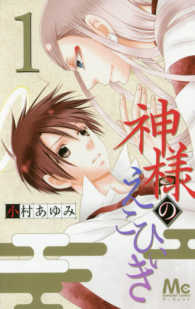出版社内容情報
2011年、新聞・テレビ消滅。では、情報はどこに集まるのか? マス消滅後に、人の「つながり」で情報を共有する時代への指針を鮮やかに描く。
内容説明
テレビ、新聞、出版、広告―。マスコミが亡び、情報の常識は決定的に変わった。ツイッター、フェイスブック、フォースクエアなど、人と人の「つながり」を介して情報をやりとりする時代が来たのだ。そこには人を軸にした、新しい情報圏が生まれている。いまやだれもが自ら情報を選んで、意味づけし、みんなと共有する「一億総キュレーション」の時代なのである。シェア、ソーシャル、チェックインなどの新現象を読み解きながら、大変化の本質をえぐる、渾身の情報社会論。
目次
プロローグ ジョゼフ・ヨアキムの物語
第1章 無数のビオトープが生まれている
第2章 背伸び記号消費の終焉
第3章 「視座にチェックインする」という新たなパラダイム
第4章 キュレーションの時代
第5章 私たちはグローバルな世界とつながっていく
著者等紹介
佐々木俊尚[ササキトシナオ]
1961年生まれ。早稲田大学政経学部中退。毎日新聞記者、月刊アスキー編集部を経てフリージャーナリスト。総務省情報通信タスクフォース委員。ITジャーナリスト(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
oser(読書家ではありませんドクシャーです)
51
最近、SNS界隈でよく聞かれる「キュレーション」という言葉について柔らかく書かれた(刊行が2011年とあり、まだインスタが全権を得てない時期で…この人、先見の明があるなぁ…)とても良い本。 …読んでいくとSNSやITといった分野は常に最先端を模索、検索とスピードが命のようで…キュレーターやアンビエント化、グローバル化などと言うと良さげに聞こえるが…ーん大変そう。おっさんのワイには情報の奔流に溺れそうで無理(佐々木さん、齢60を越えるのにアグレッシブやなぁと本の内容とはまったく無関係な感想を持ちもち)2023/10/13
mitei
50
キュレーションという言葉の意味がよくわかった。たしかに今の時代に出世などのステータスでものを買うのにはなんか違和感を感じる。2011/05/21
Willie the Wildcat
43
人と人の繋がりの多様化。価値観の創造。気づき、選定、新たな意味・価値付けした上での共有。視点・視座が差別化であり、”情報”流通への気づきが鍵。「共有」もキーワード。営利性から社会性。『読メ』が頭に浮かぶ。結果論としての営利という印象。プラットフォームのあり方も問われる。日々の生活に”宝”が埋もれているんだなぁ、と再認識と若干の反省。(汗)2014/04/26
どんぐり
41
さほど目新しいことを書いているわけではない。情報のノイズの海から自分の価値観や世界観に基づいて情報を拾い上げ、そこに新たな意味を与え、そして多くの人と共有するキュレーションについて論じた本。だれもが簡単に情報を発信しアクセスできる時代、時には情報をシャットアウトする生き方をしたいものだ。2014/05/19
佐治駿河
33
まずは私が「キュレーション」という単語にピンとこなかったのでキュレーションを調べると「何らかのテーマや価値観などに基づいて,事物を選択・分類・提示し共有すること。」となっています。以前にも佐々木さんの書籍を読んだことがありますが、そこには人と人の繋がりについて書かれていました。本書もキュレーションを軸にいくつかの題材の価値観の共有などを人とのつながり方の時代による変化を記しているように受け止めることが出来ました。それにしても15年も前にこの内容で書かれている佐々木さんは尊敬してしまいます。2025/12/24