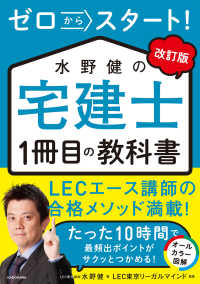内容説明
「日本語の哲学」を目指すとは、いったいどんなことなのか。―少なくともそれは、古代ギリシャに始まった西洋の哲学をただ日本語で受容する、ということではないはずである。かつて和辻哲郎が挑んだその課題は、いま、もっとも挑戦しがいのあるテーマとして研究者を待ちかまえている。ここに展開するのは、パルメニデス、デカルト、ハイデッガーといった哲学者たちと、「日本語」をもって切りむすぶ、知的バトルの数々である。これまでに類を見ない知的冒険の姿がここにある。
目次
第1章 日本語と哲学
第2章 デカルトに挑む(学問語と日常語のたたかい;「私」がきりひらく道)
第3章 「ある」の難関(パルメニデス;ヘーゲルの苦闘)
第4章 ハイデッガーと和辻哲郎
第5章 「もの」の意味
第6章 「こと」の意味
著者等紹介
長谷川三千子[ハセガワミチコ]
1946年東京生まれ。東京大学文学部(哲学科)卒業。同大学院博士課程中退。東京大学文学部助手を経て、埼玉大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nchiba
6
「考える」ためには言葉が必要である。そしてその時に使う言葉が考える事を縛る。そう考えたときに哲学のために日本語が成しうることは何か。「日本語の哲学」はまだまだ開拓の余地があるというか、入口にさしかかったところなのだということが分った。著者の考えに興味を持ったのでさらに何冊か著作を読んでみることにする。2011/08/10
ken
5
「存在者」ではなく「存在」を問うのが哲学であり、その哲学は「言葉」によってなされるものであるとすれば、日本語にとって「存在」とはどのようなものか。また、日本語話者にとって「存在」とはどのように了解されているのか。その思索の糸口を日本語の「こと」と「もの」に見いだすのが本書。「ある」にまつわるアポリアを概括する前半では、筆者が何をやりたいのかいまいちピンと来なかったが、「もの」や「こと」を論じながら、日本語による世界認識を明らかにしていこうとする後半で大方飲み込めた。総じて哲学というより言語論といった趣。2021/04/22
sk
5
デカルトや和辻哲郎などの議論に鋭く切り込んでいき、日本語による哲学を批判的に展開。刺激的な本。2017/05/22
Akiro OUED
3
「ある」と「ない」をルビンの壺の絵に例えたのは面白い。「ある」と「ない」はワンセットだからね。「我思う、故に我あり」の「我」は、「汝」で置換可能だけど、著者には思い至らなかった。コギトの焦点は、「我」ではなくて「思う」にある。著者の哲学観が見当たらない。コピペが多い。駄本。2023/02/05
take
3
「もの」「こと」の考察はとても楽しく、特に「もの」という語の奥深さ・恐ろしさに心を奪われた。2016/03/02