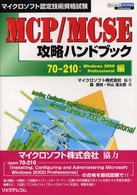内容説明
古代の列島社会は、内と外が交錯しあうアジアのネットワークの舞台である。大王と異なるチャンネルで朝鮮諸国と結びつき、国内の政治を牽制する豪族たち。渡来人や留学生によって運ばれる技術・文化、そして政治的な思惑。外交と交易を独占し、中華的な国家形成を目指す日本王権と、国家の枠を飛び越え成長する国際商人の動き。倭国の時代から、律令国家成立以後まで、歴史を動かし続けた「人の交流」を、実証的に再現し、国家間関係として描かれがちな古代日本とアジアの関係史を捉え直す。
目次
序章 列島の古代史とアジア史を結ぶ視座
第1章 アジア史のなかの倭国史
第2章 渡来の身体と技能・文化
第3章 血と知のアジアンネットワーク
第4章 天皇制と中華思想
第5章 国際商人の時代へ
第6章 国際交易の拡大と社会変動
第7章 列島の南から
著者等紹介
田中史生[タナカフミオ]
1967年福岡県に生まれる。國學院大學大学院文学研究科日本史学専攻博士課程後期修了、博士(歴史学)。関東学院大学経済学部教授。専門は日本古代史。地域史や国際交流史研究を通し、列島社会の歴史的多元性・多様性・国際性の解明をすすめている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はちめ
7
古代日本における東アジアとの交流が想像も踏まえながら羅列されている感が否めない。様々な資料に基づいているとはいえ、資料自体の信憑性が問われる時代でもあり、今ひとつリアリティが感じられなかった。国境という概念がない時代の交流史であり、現代の常識を拭い去ってアプローチする必要があるのは分かるが、その意味でももう少し実証的なアプローチが必要なのではないだろうか。☆☆☆★2022/10/18
はちめ
5
再読。このテーマの場合、日本だけではなく朝鮮半島、中国の歴史を把握する必要があり、それらをつなげることにより立体的な歴史が再現される。特に九州北部と朝鮮半島南部との関係はある意味、現代より密接な関係にあり、この事は古代における日本列島のあり方を考える上において極めて重要なことである。細かい話だが、9世紀に新羅の海賊が博多湾で日本の船を襲ったことが記録されているのは知らなかった。☆☆☆☆★2019/05/27
2n2n
4
日本の古代において東アジア諸国との対外交流・交易が国家形成や国内政治など日本の歴史にどのような影響を与えたかを詳述した一冊。よく日本は外交下手と言われるが、本書はそもそも外交とは何か、外交とはいかにあるべきかを歴史から学ぶ格好の材料であると思う。2013/06/09
つゆ
2
つまらない、、。2022/02/17
ノックアウト
2
古代日本のダイナミックな歴史を感じることができる一冊。2010/04/26
-
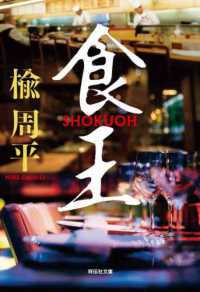
- 和書
- 食王 祥伝社文庫