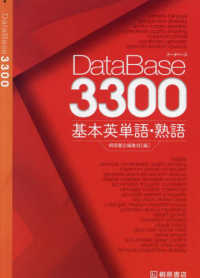内容説明
団地、ニュータウン、新興住宅地―。戦後日本の「郊外」と呼ばれる社会は、高度経済成長と相関し、都市に付属する空間として作り出された場所である。そこでは住居やライフスタイルまでが商品として購入され、住み続けることのなかにブランド志向が伴われてきた。こうした「郊外」は現代人の宿命でありながらも、その重層性と移ろいやすさゆえに、そこに生きる人びとの欲望や社会構造は、これまで十分に描き出されてこなかった。この本では、郊外生活者としての自身の経験と都市社会学の知見を結びながら、郊外という場所を生み出したメカニズムを考察する。郊外を生きる人びとの生に言葉を与える試み。
目次
序章 郊外を生きるということ
第1章 虚構のような街
第2章 この立場なき場所
第3章 郊外を縦断する
第4章 住むことの神話と現実
第5章 演技する「ハコ」
結章 郊外の終わり?
著者等紹介
若林幹夫[ワカバヤシミキオ]
1962年生まれ。1990年東京大学大学院社会学研究科博士課程中退。1993年同大学より博士号取得。早稲田大学教育・総合科学学術院教授。専攻は社会学、都市論、メディア論。文学、映画、ジャーナリズムの言説空間と社会学理論を切り結び、明晰な思考で社会構造を探究する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
katoyann
19
2007年刊。高度経済成長期以降、産業構造の変化に伴い、都市に付属した居住空間としての郊外が続々と生まれていった。本書は、郊外をライフスタイルや構成員が均質化された空間という既存の視点にメスを入れ、ニュータウンや団地には、かつてはあった封建的な地域のしがらみからの解放が希求されていたとしている。また、郊外にも分類があり、電車の路線によっては郊外化が不十分な地域もあるという知見が面白かった。単身世帯や夫婦のみの世帯が増えている現状では、わざわざ持ち家を作るニーズがないため、郊外化は終わったとしている。2025/09/03
むとうさん
8
ふらっと図書館で見つけて手にとった本。薄っぺらい「ファスト風土」などと批判されてきた「郊外」に対して、郊外ならではの重層さがあるというのが一応メインの主張なのかな。表向き「ファスト風土的見方を否定するわけではない」と書いていたけれど、「郊外」を生きるプロ(?)である著者にとって従来の郊外論が「外部の人間がぐちゃぐちゃ言ってる」もので、それに物申したいというスタンスで書かれた本だなぁという印象がある。その辺も含めて、具体例がどうしても東京圏中心になっていて、どこまで普遍的なのかはよくわからない。2014/08/10
よしよし
4
◇とりわけ都会に出て「茶の間のある家」で「家庭」を営む人々にとってそれは、都会の茶の間のある家で暮らしていても心のよりどころやアンデンティティの根拠は「いなか」のいろり端のある家とそこで暮らす「家」家族にあるというように、社会的な所属や意識の二重構造でもある。◆自分の根/ルーツを深く理解し、意識しながら歩んでいきたい。2020/04/22
ケー
4
いかにも新書といった内容。学生のころにもう少し真剣に読んどけばよかったかなぁとちょい後悔。常に複数の視点から郊外を捉えようとする筆者の姿勢がよかった。2016/03/30
msykst
4
再読。郊外文化への批判は多い。しかし郊外は社会変動の必然として生まれたものであり、そこでの文化は「郊外という場所を生み出した社会の構造やメカニズムに深く根ざし、条件づけられている」(P220)。マスメディアや消費文化に媒介されたアイデンティティのあり方を所与のものとし、「希薄なものの分厚い厚み」を論じる本書は、安易な郊外への批判言説(か、それへの対抗を目的化した言説)ばかりの現状の中で非常に重要な存在だと思う。2009/09/30