内容説明
病み衰えて末期の状態にある人は死ぬほかない―。死の哲学はそう考える。しかし死にゆく人にもその人固有の生命がある。死の哲学はそれを見ようとせず、生と死の二者択一を言い立てる。ソクラテスもハイデッガーもレヴィナスも、この哲学の系譜にある。そのような二者択一に抗すること。死へ向かう病人の生を肯定し擁護すること。本書はプラトン、パスカル、デリダ、フーコーといった、肉体的な生存の次元を肯定し擁護する哲学の系譜を取り出し、死の哲学から病いの哲学への転換を企てる、比類なき書である。
目次
1 プラトンと尊厳死―プラトン『パイドン』
2 ハイデッガーと末期状態―ハイデッガー『存在と時間』
3 レヴィナスと臓器移植―レヴィナス『存在の彼方へ』
4 病人の(ための)祈り―パスカル、マルセル、ジャン=リュック・ナンシー
5 病人の役割―パーソンズ
6 病人の科学―フーコー
著者等紹介
小泉義之[コイズミヨシユキ]
1954年札幌市生まれ。1988年、東京大学大学院人文科学研究科博士課程哲学専攻退学。立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。哲学・倫理学を専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
井月 奎(いづき けい)
32
優れた思想書は読み手の思想を一度解体して再構築させます。その際に形よく、または意識的にいびつになるように気付きを与えるのです。本書は数人の偉大な思想家、哲学者の書から生と死の関係と死の意味をとりだして吟味して、命ありき、生ありきの考え方を貫いており、考えが深く鋭くなると陥りがちな細部へのこだわり、死への甘美な誘惑、を断ち切ろうと筆を走らせて、死は結末ではなく、その死から何かを汲みだすことが命の意味であり、生きている者の責任であると説きます。覚悟を持ち、思考を厭わない。それが自分を自分たらしめるのです。2016/01/03
msykst
9
さすがに長くなったのでこちらで。 http://d.hatena.ne.jp/msykst/20170222/1487723117 要するに、ソクラテス、ハイデッガー、レヴィナスを引き合いに、哲学が伝統的に「生と死」という二分法に則って議論をしていた事を批判した上で、「病人の生」を肯定しようとする本です。ともすれば臨床やケーススタディみたいな「現場」の話に基いて論じられる尊厳死や安楽死について、徹頭徹尾哲学的に突き詰める感じには、結構感動と凄みを覚えたです。2017/02/21
まつゆう
4
この筆者の本は一通り読んだが「生殖の哲学」と併せて、かなり応用・先端倫理に「寄せている」印象を受ける。ただ知識欲を満たしたいがため(明け透けにいえば哲学をかじって知的な自分にならんとするため)に読むのはお勧めしない。筆者の念頭の思い―哲学の言葉で語ることで、何を守り、誰に代わり訴え、何を批判しているか、(病者の生、誰かの自由を奪いながら、生命を消すことは許されないという信条、また、現実には誰かの命で飯を食っている奴がいるという事実の糾弾のため、と個人的には読んだ)を追走して読み、そして使うことが肝要かと。2014/09/06
瀬希瑞 世季子
2
読了後、TENG GANG STARの「きっと」を聴くとこの本が目指す光景がちょっと見えるかもしれない。 https://youtu.be/5bKW9JXc1is2023/07/15
koi
1
印象に残ったのは、「人間を家畜として見るなら、誰が死を配分するのか」という問い。 戦争や災害、貧困や差別の中で、命が自然に消えていくんじゃなくて、「誰か」が「生きるべき人」「死んでいい人」を決めてる。 旧約聖書で、父アブラハムが息子イサクを神に捧げようとする場面について「世界のいたるところで、現代のアブラハムとイサクは、これは自殺ではない、これは他殺ではないと言い合いながら、死に駆り立てられ、殺されているのだ。」人が人を犠牲にする社会。 今回、あまり読みきれていない感じがするからまた読み返そう。 2025/07/31
-
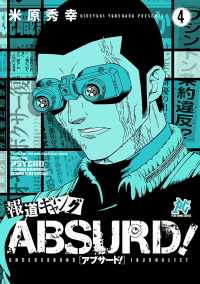
- 電子書籍
- 報道ギャングABSURD! 〈4〉 プ…
-
![早わかり日本史 流れを重視した[解説+図解]。学び直しに最適! 知的生きかた文庫](../images/goods/ar2/web/eimgdata/9989205949.jpg)
- 電子書籍
- 早わかり日本史 流れを重視した[解説+…







