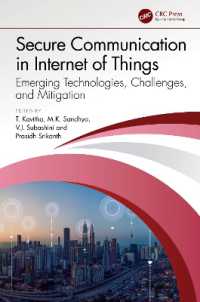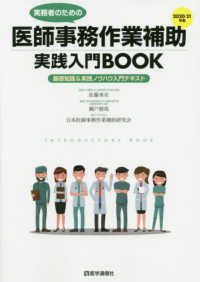内容説明
“動機”の理解が難しいために、その質や量に比べて、少年非行・犯罪はしばしばセンセーショナルに取り上げられがちである。しかし、近年の脳科学の著しい発達はその不透明な部分を少しずつ解明し、犯罪を構成する要素の意外な姿が浮かび上がってきている。「対人関係」や「想像力」などに強い偏りを見せるアスペルガー障害と非行特性との関係を明らかにするなど、少年非行・犯罪の分野で新しい局面を切り開いてきた著者が、メディアや家族、性差、精神医学などの視点から自らの体験を再検討し、事態のより正確な把握を試みる。
目次
第1章 事件の現場を歩く
第2章 FBIを翻弄した爆弾魔
第3章 十九歳の死刑囚
第4章 脳と犯罪の不思議な関係
第5章 非行のメカニズムを読みとく
第6章 「動機」とは何だろうか
著者等紹介
藤川洋子[フジカワヨウコ]
1951年生まれ。73年、大阪大学文学部(哲学科)卒業。同年、家庭裁判所調査官補。その後、各地の家裁勤務を経て、大阪家庭裁判所総括主任家裁調査官。東京大学医学部客員研究員も兼ねる
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
18
犯罪を行った少年の中にアスペルガー障害の人がおり、そこを理解しないと冤罪につながる、という趣旨の本だと理解した。アスペルガーや自閉症スペクトラムの人への差別につながらなければよいのだが、と懸念しつつも、こうした症例がありうることも知っておかねばいけないとは感じた。社会の理解が(少年犯罪に限らず)犯罪を防止するのである。2013/12/02
おらひらお
5
2005年初版。少年犯罪の現場に立つ家裁調査官がまとめた本です。現場に立つ人間が本を書くのはかなり難しいところでしょうが、一般の人々にでもわかりやすいものとなっています。犯罪には脳の障害の影響も考える必要があることが再確認できました。これも好著。珍しく読んでよかった本が続きました(喜)。2012/09/28
Tai
3
家裁の調査官が独自の視点でまとめた本。実際の体験をもとに書かれており、非常に読みやすかった。ただ、自閉症スペクトラム障害がかかわっている件ばかり掲載され、まるでアスペや自閉症の子が犯罪を引き起こすかのような錯覚にもとらわれる(この件に関しては著者も本書105ページで断りをいれている)のが危険といえば危険だ。自閉症やアスペに対して、むやみに危機感を煽るような気もする。(図)2013/06/06
つな子
2
2005年の刊である。ゼロ年代教育学部の学生であった。当時、発達障害はどの講義でも取り上げられた。その匂いを起こさせる。肝要の内容はというと「生物学的要因の検討」と副題につけてもよいのではと思う。だがつけないことによって旧来的愛情観によって少年犯罪を眺めたい面々を刺激することができると思えば意図的か。幾つかのケースと見解が筆者の情感とともに記述される。今更、と言いたくなる内容も多いが当時の研究者実務家のお陰で発達障害の認知が(誤解と偏見を伴いつつ)広まったのか、と思えば貴重な意見書だったろう。2014/06/12
クェーサー
2
三食キチンと食わすと大抵の非行少年は落ち着いてくるってすげえと思った。 後、脳の問題を理解しての対処ってむちゃくちゃ大事なんだなとも。2011/05/09