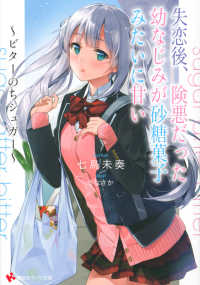内容説明
小学校から大学まで、日本の学力低下は深刻な惨状を呈している。にもかかわらず、「ゆとり教育」は着実に進められつつある。著者が豊富なデータに基づいて指摘した理数系の弱さへの対策も、手付かずのままである。実は数学力に限っていえば、昭和三〇年代後半から五〇年代前半の数学教育は充実したものだった。当時、激化しつつあった受験戦争が批判されたが、日本の数学力は常に高い水準を維持していたのである。数学教育は、どこで間違えたのだろうか。国際的に抜きんでた数学力を回復するための方法を、海外比較を交えて提案する。
目次
第1章 大転換したアメリカの教育
第2章 数学者の見た教育問題
第3章 分数ができない大学生
第4章 勉強しない子供たち
第5章 フランスの学力のきたえ方
第6章 「ゆとり教育」はなぜ悪いか
第7章 日本の教育の未来
著者等紹介
戸瀬信之[トセノブユキ]
1959年富山県生まれ。83年、東京大学理学部(数学科)卒業。愛媛大学、東京大学、北海道大学を経て、現在は慶応大学経済学部教授。この間、パリ第13大学でも教える。理学博士。専攻は代数解析学。現在、日本数学会理事、日本私立大学連盟教育研究委員会分科会委員などもつとめる
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nchiba
2
ゆとり教育の弊害に対する危機感はわかった。というか、現実にこの世代の子供を持つ僕に取っては言うまでもないという感じのことを何度も書いている気がしてあまり読みやすい本ではなかったな。2010/08/25
アルゴン
1
★★★★ 世の中全体の傾向として「必要なことしかやらない」という効率主義がはびこっているのを感じます。これだけ情報量の多い現代、その選択をとってしまいがちなのは分かりますし、自分も一時期そうしてましたが、どうも仕入れたものが定着しない。一見不要であっても必要なことは多いです。教育論に根拠がないのはその通りで、そのために教育学者は言いたい放題。それに怒りを覚えるのは分かりますし、それを私たちが知る機会はあまりないので書いていただけるのも貴重。ただ構成はもう少し考えてほしかった。2014/07/27
Happy Like a Honeybee
0
分数ができないなど、大学生の学力低下を記す書物。 この背景は文化リテラシーの違いだろうか。 平等教育からエリートを生み出す教育こそが、将来の日本に必要ではなかろうか? 2014/04/18
-
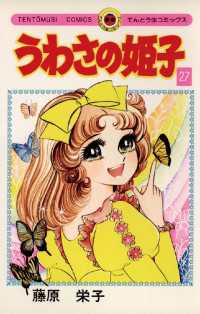
- 電子書籍
- うわさの姫子(27) てんとう虫コミッ…