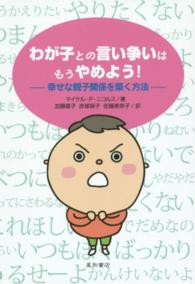内容説明
優れた認識、応用力の高いたくましい知識を身につけるには、どうしたらよいか?その途のエキスパートが培った「勉強法」や「ノウハウ」をどのように理解するか?本書では、人間の知的活動を研究する認識心理学・教育心理学から、学んだり教えたりするときの心の働きに、まず本質的問いを発する。その上に立って学習法や教育のあり方を描き、ひいては人間の成長・発達について進むべき方向を案内する。
目次
第1章 内面からの発想―基本的問い(意味移植にたとえる;スレ違いへの感度―ハトは何羽? ほか)
第2章 認識をうながす方法―目覚ましの機能(課題研究の重要性―卒業研究の体験から;認識形成の流れ―問題解決の三段階 ほか)
第3章 認識に熟達する方略―エキスパートの驚異の練習法(英語会話能力をつける―くり返しの効用;テストに対処する法―受験数学 ほか)
第4章 ネットワーク型認識への接近―壁をこえて(認識の特徴―エキスパートの記憶力;抽象と具象の壁―生活文化の束縛 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
繭希
0
1年生算数の仲間集め。子「絵の中にいるが他の動物と離れているので仲間じゃない」認識のズレは必ずある。それを無視した教え込みは子の意味構造を破壊する。大人はズレを疑問に思い成長に繋げられる★研究の認識形成…問題発見(興味)、問題定義(仮説)、問題解決★実態に触れるフィールドスタディ。現場で見て当事者意識と疑問★能力は場面依存的★抽象だけを教えても具体に適用できない。熟練者は抽象が理解できているので抽象からが良いと考えてしまう。国際比較研究で「計算はできても応用はできない」のは慣れない問い方だから?2016/07/15
たみ
0
自分の認識と他者の認識は背景や経験により異なる事を改めて認識させられました。同じような日々、接する人もほぼ同じという生活をしているので、自分の認識も偏りがあるんだろうな…と。2016/04/13
フィ
0
認知心理学、教育心理学から見た内容であったが、今まで読んだ勉強本には見られない内容があり参考となる点が多くあった。実際にどのように応用していくかは良く考えて見たい。2013/06/09