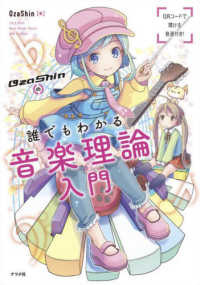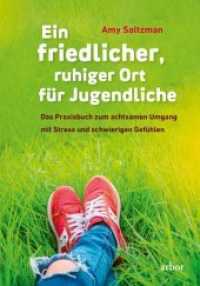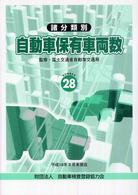内容説明
アジア大陸の縁辺に位置し、大きな暖流と寒流に取り巻かれた日本列島は、今日まで豊かな水産資源の恵みを私たちに与えつづけてきた。日本人はどのように魚と共存してきたのか。アユ漁とアワビ採取を中心に水産利用の祖型を探るとともに、ハマチとクルマエビを例にとり、戦後の産業化と国際化の歩みをたどる。稲作農耕システムを社会基盤に置きながらも複合的な文化形態を成熟させてきた日本民族の漁業文化に光をあてた異色の「サカナと日本人」論。
目次
第1章 ハマチ―海産魚養殖の挑戦者が生き延びる戦略
第2章 クルマエビ―国際化と地域主義の共存を迫る
第3章 コイ―日本人の郷愁の魚はよみがえるか
第4章 ニジマス―気位の高い地球上の大歩行者
第5章 アワビ―縄文文化と弥生文化の違いを探る
第6章 アユ―清流の女王か、おちぶれる手弱女か
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
0
柳田や網野,ダーウィンや常一を援用しながら語られる良書。大正4年まで漁業生産量は220万tであり4割は輸出だった。鮭,鱒,蟹は富裕層しか食べず殆どの日本人は消費せずに鯵,鰯を食べた。S30年代から肉,卵の消費と共に魚消費が伸びただけ。上層で重宝されたのが鯉(近世に鯛に)。庶民はあくまでドジョウ,鮒。ケミカル包装の発達が保存期間を伸した。安曇野に巨体な虹鱒の養殖場があるとは知らなかった。「長野県は"水産県"の一つである」養鯉は,養蚕が発達すると蛹が良い飼料になる為,相互に伸びる。欧米とは違う調和の自然誌2014/09/08
-

- 和書
- 今、ここに生きる預言書