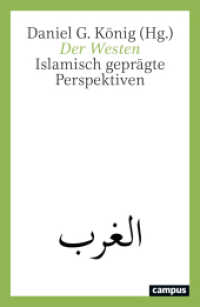内容説明
モーツァルトやヨハン・シュトラウスなど多くの楽聖たちが名曲を生んだ音楽の都ウィーン。神聖ローマ帝国皇帝ハプスブルク家の都ウィーン。ヨーロッパの古都は今もなお優雅で華やかな香気を放っている。だが、このような都市の神話はいったいどのようにつくられたのだろうか。ローマ人が築いた駐屯地にはじまり、都市計画による大改造にいたるまでの激動の都市形成の歴史をたどりつつ、「よそもの」を魅きつける魔力とオペレッタ的いかがわしさにみちた、ウィーン神話のもうひとつの顔に光をあてる都市の社会史。
目次
1 ウィーンの成立(ローマの駐屯地ウィーン;ウィーンの暗黒時代 ほか)
2 バロック的なるウィーン(ウィーン存亡の危機;マリア・テレージアのウィーン ほか)
3 ウィーン神話(一九世紀の足音;ビーダーマイアーからバリケードへ ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
sun
6
「音楽の都」ウィーンの歴史。「よそものがつくった」という言葉に魅かれて読んだ。もちろん音楽家の話も載っていて、あっ、こうゆう事か。とすっきりする解説もあり、ありがたい。良書。2015/04/18
*takahiro✩
4
とても読みやすく、まさに知りたいことが網羅されていて一気に読み終えました。目的達成です。これに近いと思われる本が他にもある中でこの本を選んで良かったです。ドイツ語が分からないのでGriechenbeislがギリシャ(Griechenland)の食堂だったとは今まで気がつきませんでした。文字にして読めばそのとおりなのですが…。ドイツ語のオペラが生まれた経緯も初めて知りました。2018/05/18
錆紫
2
ハプスブルク帝国の都として、あるいは中欧の要衝としてのウィーンに、どこからどういう人が集まってきたのか、というような話の本。「よそもの」をキーワードにした通史という体裁をとっているが、著者の専門からして、音楽・演劇関係の話が強い。他方、歴史読み物としてはちょっと中途半端で、世紀末ウィーン以降の話はわからないし、それゆえ、「よそもの」の寄せ集めであったオーストリアがナショナリズムに飲み込まれてぽしゃってしまうあたりも書かれていない。2014/09/13
とみしん tomisin555
1
元旦の夜に、ウイーンフィルのニューイヤーコンサートを観ていて、ふと数年前にどこかの古本市でウイーン本の新書を買って、例によって積読状態にしていることを思い出し、読んでみようということになった。今年の1冊目だ。読了まで随分時間がかかってしまったけれど、面白くなかったわけじゃない。世界有数の観光都市がどういうように形成されていったのか。「よそもの」がつくった都市、というサブタイトルがとてもいい。僕は基本都市論好きなので、こういうのをもっと読みたい。で一番印象に残ったのは、やっぱりマリア・テレージアだな。2019/01/23
小瑠璃
1
同じく新書で読み終えたばかりの「モーツァルト~天才の秘密~」が格別読みやすかったので余計思うのかもしれませんが、ザ・新書 な難易度でした。あまり呑気には読めません。楽しむには歴史の知識はある程度必要で、ウィーンの地理を文と図だけで思い浮かべるのはなかなか困難でした。面白かったのは"ウィーンでは過去が理想化される""観光時代はウィーン神話を完成した"などという考え方。それに、カフェ文化の話。ウィーンの珈琲の種類は200に達し、こだわるポイントは日本のように豆の種類でなく"たてかた"なんだとか。2015/01/15
-
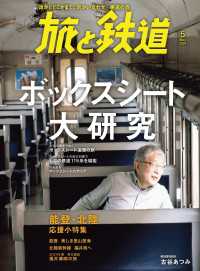
- 電子書籍
- 旅と鉄道2024年5月号 ボックスシー…