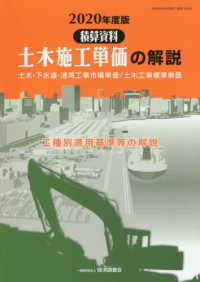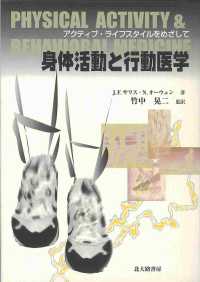内容説明
真理の最高決定機関であるはずの理性が人間を欺く二枚舌をもつとしたら、一大事ではないだろうか。この理性の欺瞞性というショッキングな事実の発見こそが、カント哲学の出発点であった。規則正しい日課である午後の散歩をするカントの孤独の影は、あらゆる見かけやまやかしを許さず、そのような理性の欺瞞的本性に果敢に挑む孤高の哲学者の勇姿でもあったのだ。彼の生涯を貫いた「内面のドラマ」に光をあて、哲学史上不朽の遺産である『純粋理性批判』を中心に、その哲学の核心を明快に読み解き、現代に甦る生き生きとした新たなカント像を描く。
目次
第1章 純粋理性のアイデンティティー
第2章 カント哲学の土壌と根―批判哲学への道
第3章 迷宮からの脱出―第一アンチノミーの解決
第4章 真理の論理学―経験世界の脈絡
第5章 自然因果の彼岸―自由と道徳法則
第6章 自由と融合する自然―反省の世界
第7章 理性に照らされる宗教
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ehirano1
96
「私たちは経験と思い込みで物事を見ている」という前提は日常の行動においてなぜか忘れがち。この前提をできるだけ忘れないようにすれば、相互尊重が達成され、その先にある「平和」が訪れる。とにもかくにも、「経験」が重要で、「考えること」も経験の1つ。読書では『代理体験』という貴重な経験もできますね。2024/07/10
青蓮
86
カント哲学は以前から興味がありましたが難解そうで手が出せずにいました。一先ず解りやすそうな入門書からと思い、本書を手に取りました。哲学の知識がほぼゼロに等しい私にはやっぱり難しかったです。が、非常に興味深く読みました。人の理性の欺瞞を暴き、理論建てて展開していく論理は道徳法則、ついには宗教論にまで至る。宗教論はもっと知りたいなと思いました。今の私の理解度ではカントの著作そのものを読むにはハードルが高いですが、何時か挑戦したい。難しいながらも本書は入門書として良い本だと思います。再読必須。2019/05/20
初美マリン
85
この本は全くので初心者の自分が読んでも具体的な例を挟んでくれてわかりやすい。図解もしてくれたのだが、自分には理解不能だった。カントというと身構えたが、相互主観的に考えるなど、身近に意識できる表現は、嬉しかった。まあしかし理解できたのは1%もないだろうけど、今さらであるが、読むことができてよかった。読友さんに感謝!2024/11/23
ももたろう
33
認識について気になり、カントの「純粋理性批判」を手に取るも、あっけなく挫折。あれは気力と体力と何より時間がたっぷりあるような人(大学生とか、高等遊民とか)じゃないと、社会人がゼロから読み解くのは厳しいと感じた。でも悔しいので入門書を手に取るも、入門書なのに難しい。理性批判、テーゼとアンチテーゼ、アンチノミー(二律背反)、そのあたりまで何とか理解したような気になったけど、ヒュームの因果律批判がカントをして理性批判に向かわしめたのが何故なのかよく分からなくなってしまった。何度か読めば理解できそう。また読もう。2017/08/29
フム
32
再読。以前の読書会で『イェルサレムのアイヒマン』を読んでいた時に、アイヒマンはカントを読んでいた、というのが印象に残って、この入門書を読んだ。カント哲学は「理性批判」という一言で総称されるという。理性とは常識的には真理や正義の拠り所であり、それ自身の中に誤謬や悪の種を含んでいるとは考えにくい。その理性が人間を欺く本性をもっているとすれば一大事である。カントが発見したのはそのような理性の欺瞞的本性だった。などと、線を引いた箇所を読み返すとおもしろい。やはりもう少し理解できるようになりたい。2019/11/28
-

- 電子書籍
- 週刊SPA! 2014/5/27号