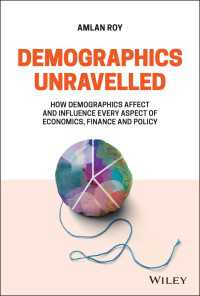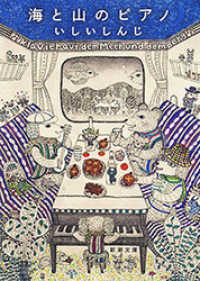出版社内容情報
通説を覆す「東京漫才」の始まり、戦後のメディアと連動した復興、MANZAIブームから爆笑問題、ナイツの活躍まで余すところなく描く画期的「東京」漫才史。
内容説明
現在も人気のある日本の伝統的芸能「漫才」には「お笑い論」の書籍は数多く存在するが、「漫才」の、特に東京を地盤とした漫才の歴史に関する書籍は数少ない。この「東京漫才」に焦点を当て、漫才の源流にまで遡り、「東京漫才の元祖は誰か?」、「しゃべくり漫才の流入と定着」、「戦後東京漫才の御三家」、「東京漫才専門寄席」、「MANZAIブームの功罪」、「爆笑問題、ナイツの活躍」等をテーマに、その発生と栄枯盛衰を、通説の誤解を正しつつ記した、画期的な「東京漫才」通史。
目次
序章 「漫才」以前
第1章 東京に漫才がやってきた
第2章 生まれる東京漫才
第3章 戦前の黄金時代
第4章 戦争と東京漫才
第5章 焼け跡から立ち上がる
第6章 東京漫才の隆盛
第7章 MANZAIブームと東京漫才
終章 新しい東京漫才の形
著者等紹介
神保喜利彦[ジンボキリヒコ]
1996年群馬生まれ。國學院大學卒。学生の頃から芸能研究を手掛け、研究サイト『東京漫才のすべて』『上方漫才のすべて』を運営している。論文掲載もあり。演芸研究誌『藝かいな』を2021年から月刊で刊行(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
fwhd8325
52
漫才は上方の方が盛んであることは承知なのですが、子どもの頃からテレビやラジオで接してきた東京漫才も演芸を語るうえで重要な分野だと思います。上方からは澤田隆治さんをはじめ、素晴らしい著作が出版されていますが、東京漫才はこれ!と言ったものに出会っていませんでした。この著書はそんな気持ちを払拭してあまりあるほどです。素晴らしい資料です。前半は名前も知らない方々ばかりですが、よくぞここまでという気持ちです。後半に近づくにつれて知っている方が登場しますが併せて亡くなったことも書かれていて淋しい気持ちになりました。2024/05/18
gtn
30
当時の新聞等を丹念に当たった力作。文献として耐え得る最上の東京漫才史ではないか。元々関西は事務所が芸人を縛り、会社の一存で芸人を押し出せるのに対し、東京は席亭や興行主の発言力が強く、江戸から続く落語の基盤に、立場の弱い他の芸能が入り込む余地がなかった。だが、東喜代駒、林家染団治等の新趣向と努力により、1920年代にはそれなりの勢力と地位向上を得る。その先人の思いを無にしないためにも、「東京漫才の鼻祖は千太万吉」といった安直な定説を全否定するところに怒気さえ感じる。なお、著者はまだ二十代。驚くばかり。2024/01/01
緋莢
16
図書館本。祝福芸としての「萬歳」から始まり(寺社奉行が担っていたが、増加により、1600年代後半から陰陽道や天門道の土御門家が引き受けた、というのにはへぇーとなりました)、祝福芸から、芝居や流行を取り入れた「萬歳芝居」となり、そこから、演芸的な「漫才」となり、大正初期に東京へと入ってようです。そういう歴史を知るという点では興味深かったですが、名前をかろうじて知っているという人たちが出てくるのが(続く2024/05/03
スプリント
9
東京漫才の歴史をここまで詳細に書き記した本はなかったと思う。 戦前・戦中・戦後と東京の漫才師たちの変遷を理解することができる。2024/03/18
Inzaghico (Etsuko Oshita)
9
普段笑ってい観ている「お笑い」のうちの漫才の成り立ちを概観した大著。著者は1997年生まれ、よくぞまとめてくれた。面白さが増してきたのは、1980年代前後のTHE MANZAI世代以降だ。リアルタイムで経験しているのは大きい。今では不仲をネタにしている重鎮のおぼん・こぼんがTHE MANZAIのときは若手だったと驚くが、かれこれ半世紀近く前だもんな、と納得。不仲なコンビは多く、それで解散したコンビも多いが、のちに再結成していて今に至るケースも多い。不仲でも、舞台で息の合ったところを見せるのはさすがプロ。2024/03/16