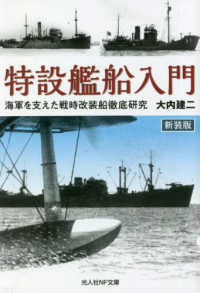出版社内容情報
高千穂・日向・出雲の景観問題解決に奔走した著者が神話の舞台を歩き、記紀編纂の場である飛鳥の遺跡に立って、古代の人々が神々に託した真意を明らかにする。
日本の神々とは日本人にとってどのような存在だったのか。神々は日本の風土のなかでどのような役割を担っているのか。日本の神は、自然を畏敬し国土の安寧を願う出雲系と、天皇による国家支配を正当化する高千穂・日向系に分かれる。高千穂・日向・出雲で景観問題の解決に奔走した著者が神話の舞台を歩き、「古事記」「日本書紀」編纂の場である飛鳥の遺跡に身を置いて、神々の来歴にひそむ謎を解く。
【目次】
序章 女神はなぜ洞窟に隠れたか――高千穂神話の世界から
第I部 出雲の神々の世界へ
第一章 スサノオの国づくりと和歌の起源――出雲平野の「わが心すがすがし」
第二章 斐伊川水系大治水計画――昭和・平成のオロチ退治
第三章 天下経営の大神――出雲大社表参道神門通りの道づくり
第四章 水に臨む神々――城原川流域委員会
第五章 疫病神の活躍――鞆の浦まちづくり
第II部 風土に生きる神々
第六章 巨大ナマズと戦う神々――要石とプレートテクトニクス
第七章 「ふるさと見分け」の方法――姥ヶ懐・裂田溝の危機
第八章 白き山の姫神――在地神と外来神
第九章 座問答――古代の大合併と合意形成の知恵
第十章 神々誕生の海岸――宮崎海岸侵食対策事業
第III部 神話から歴史への旅
第十一章 飛鳥にて――『古事記』『日本書紀』編纂スタートの地
第十二章 神話と歴史をめぐる三つの疑問
第十三章 飛鳥浄御原宮――神話と歴史を編む
第十四章 前例としての日本神話
第十五章 古代からの伝言――危機の時代のリスクマネジメント
内容説明
日本の神々とは日本人にとってどのような存在だったのか。神々は日本の風土のなかでどのような役割を担っているのか。日本の神は、自然を畏敬し国土の安寧を願う出雲系と、天皇による国家支配を正当化する高千穂・日向系に分かれる。高千穂・日向・出雲で景観問題の解決に奔走した著者が神話の舞台を歩き、「古事記」「日本書紀」編纂の場である飛鳥の遺跡に身を置いて、神々の来歴にひそむ謎を解く。
目次
序章 女神はなぜ洞窟に隠れたか―高千穂神話の世界から
第1部 出雲の神々の世界へ(スサノオの国づくりと和歌の起源―出雲平野の「我が心すがすがし」;斐伊川水系大治水計画―昭和・平成のオロチ退治;天下経営の大神―出雲大社表参道神門通りの道づくり;水に臨む神々―城原川流域委員会;疫病神の活躍―鞆の浦まちづくり)
第2部 風土に生きる神々(巨大ナマズと戦う神々―要石とプレートテクトニクス;「ふるさと見分け」の方法―姥ヶ懐・裂田溝の危機;白き山の姫神―在地神と外来神;座問答―古代の大合併と合意形成の知恵;神々誕生の海岸―宮崎海岸侵食対策事業)
第3部 神話から歴史への旅(飛鳥にて―『古事記』『日本書紀』編纂スタートの地;神話と歴史をめぐる三つの疑問;飛鳥浄御原宮―神話と歴史を編む;前例としての日本神話;古代からの伝言―危機の時代のリスクマネジメント)
著者等紹介
桑子敏雄[クワコトシオ]
1951年群馬県生まれ。哲学者。東京工業大学名誉教授。東京大学文学部哲学科卒業、同大学院博士課程修了。博士(文学)。南山大学助教授を経て、東工大工学部助教授などを歴任。1999年『環境の哲学』の上梓を契機に、建設省から政策提言を求められ、日本各地の公共事業の合意形成にかかわる。2014年一般社団法人コンセンサス・コーディネーターズを設立し、代表理事。様々な課題解決のための社会的合意形成に従事している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tamami
わ!
Junko Yamamoto
-

- 和書
- 天皇の日本史 〈2〉