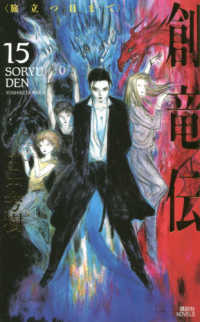出版社内容情報
「日本人は無宗教だ」とする言説の明治以来の系譜をたどり、各時代の日本人のアイデンティティ意識の変遷を解明する。宗教意識を裏側から見る日本近現代宗教史。
内容説明
「日本人は無宗教だ」とする言説は明治初期から、しかもreligionの訳語としての「宗教」という言葉が定着する前から存在していた。「日本人は無宗教だから、大切な○○が欠けている」という“欠落説”が主だったのが、一九六〇年代になると「日本人は実は無宗教ではない」「無宗教だと思っていたものは“日本教”のことだった」「自然と共生する独自の宗教伝統があるのだ」との説が拡大。言説分析の手法により、宗教をめぐる日本人のアイデンティティ意識の変遷を解明する、裏側から見た近現代宗教史。
目次
第1章 無宗教だと文明化に影響?―幕末~明治期
第2章 無宗教だと国力低下?―大正~昭和初期
第3章 無宗教だと残虐に?―終戦直後~一九五〇年代
第4章 実は無宗教ではない?―一九六〇~七〇年代
第5章 「無宗教じゃないなら何?」から「私、宗教には関係ありません」に―一九八〇~九〇年代
第6章 「無宗教の方が平和」から「無宗教川柳」まで―二〇〇〇~二〇二〇年
著者等紹介
藤原聖子[フジワラサトコ]
東京大学大学院人文社会系研究科教授。シカゴ大学Ph.D.(宗教学)。専門は比較宗教学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
14
明治日本で活動した宣教師ニコライは、「日本人には宗教心がない」という言説に反論したが、裏を返せば当時からそう見られていた証でもある。この問題を、明治時代から2020年代まで長いスパンで分析したのが本書。一口に「日本人無宗教説」と言っても、その語られ方は時代により多種多様。無宗教だから戦争で残虐行為を働いたと反省したり、逆に無宗教だから世界の宗教紛争とは無縁と胸を張ったり…猫の目の如く変ずる日本人論のいい加減さを知る上でも有益な一冊。2024/05/28
kenitirokikuti
13
ハリスやバードらが幕末の日本人について宗教がない、てなことを書いている。幕閣は無神論の儒教徒だし、庶民は呪術的な偶像崇拝に熱心だ、と。んで、その後は文明開化が求められるため、日本人が未開だったり遅れたりしているのは宗教がないからだ、という言説が広まる。国家神道で宗教力をアップして国威アップを目指したり、敗戦後は無宗教だから侵略したのだと懺悔したり、豊かになってくと、いや日本は多神教だアニミズムだと独自の宗教があるんだになり、神仏キリスト教が重なってるという言説は減ってゆく。続く2023/05/27
CCC
12
近代以降の日本の宗教についての言説をなぞることで「宗教」という言葉の恣意性が浮かび上がってくる。日本だけじゃなく西洋の視点でもキリスト教中心の見方による無神論判定があったり、かと思えば武士道を宗教扱いしたりとブレがあるのは変わらない。日本の宗教への言説は宗教がないから〇〇がないという欠落説、宗教がないから〇〇があるという充足説、日本には独自の特殊な価値観が浸透してるよという独自宗教説、これらがぐるぐる回っている状態で、何かを主張したい人の話のだしに使われて続けてきたというのがまとめになるだろうか。2023/05/29
coldsurgeon
10
日本の近現代史の中で、特に宗教史としての日本人無宗教説の系譜を調べ、論じた書です。日本人は無宗教だとはよく言われるが、それがいつごろから、どのような形で出現し、世に広まったかは興味深い事実でした。著者たちが、宗教とは、信仰とは、を定義せず、調査研究の形で記したことが、ある意味、無宗教を捉えやすくしているのかもしれない。社会に対して真摯に警鐘を鳴らしたい人達にとって、無宗教説は、細かい説明抜きに自分の主張を他者に伝えるのに効果的な手段であったことが窺える。多神教が感ずる宗教だとすれば、一神教は信ずる宗教だ。2023/10/06
氷月
5
幕末明治の頃からすでに存在していた「日本人無宗教説」の歴史。時代によって内容の変遷はあるが、型としては次の三パターンがループしているだけだという。すなわち、「無宗教だから日本人には〇〇がない」という「欠落説」、「むしろ無宗教な日本人は凄い」という「充足説」、「いや日本人の宗教は『大和魂』『アニミズム』etcだ」という「独自宗教説」。公共機関やそれに準じるような組織の神事に関する訴訟に対する判決理由が、日本人無宗教説の変遷を反映しているのも面白かった。2024/09/09
-
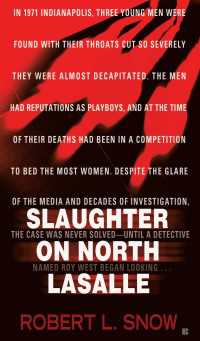
- 洋書電子書籍
- Slaughter on North …




![JTB完全監修 ころんとかわいい7ポケット超軽量巾着バッグBOOK [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/42990/4299064968.jpg)