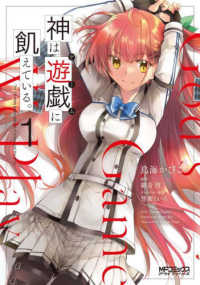出版社内容情報
中世ドイツ・ハーメルンの「笛吹き男」伝説。一三〇名に及ぶ子供たちが突如消えた事件である。「東方植民」の視点から真相に迫り、ドイツ史における系譜を探る。
内容説明
中世ドイツ・ハーメルンで起きた「笛吹き男」伝説。約一三〇名におよぶ子供たちが突如消えた事件として知られる。その真相は、歴史の闇に隠れ、解明は困難であるとされてきた。諸説あるなか、本書は、事件が東方植民へのリクルートの際に発生したという説に立つが、問題はそこで終わらない。この東方植民をキーワードにすると、ドイツ史の暗部が見えてくる。
目次
序章 「笛吹き男」ミステリーの変貌
第1章 「笛吹き男」伝説の虚像と実像
第2章 事件に関する諸説
第3章 ハーメルンで起きた事件の検証
第4章 ロカトールの正体と東方植民者の日常
第5章 ドイツ東方植民の系譜
第6章 ドイツ帝国(一八七一‐一九一八)の植民地政策
第7章 ナチスと東方植民運動
第8章 「笛吹き男」とヒトラー
著者等紹介
浜本隆志[ハマモトタカシ]
1944年香川県生まれ。関西大学名誉教授。ワイマル古典文学研究所、ジーゲン大学留学。博士(文学)。ドイツ文化論・ヨーロッパ文化論専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
109
グリム童話で有名な「ハーメルンの笛吹き男」は、隣接地に同じ民族を移住させる東方植民のリクルートに際して起きた事件が原型と見る。当時の風俗習慣や残された資料、植民活動に従事した修道会の歴史を傍証とした推理は、下手なミステリも及ばない鮮やかさで納得させられる。東方への拡大衝動はドイツの生存圏獲得を至上とするヒトラーによって国策に採用され、第二の笛吹き男となった彼の煽動下で東欧やロシアのドイツ化政策が進められた。人命を使い捨てる思想が数百年後に大量虐殺へ発展する有様は、政治が生み出した幻想の恐怖を禍々しく示す。2023/03/06
まーくん
96
阿部謹也の『ハーメルンの笛吹き男』はドイツの小さな町ハーメルンで700年前に起きたとされる、「笛吹き男に連れられ130人の子供たちが失踪した」という伝説の真相を探ることにより、中世の社会、民衆の暮らしや文化を生き生きと描いて見せた。しかし伝説の本丸を包囲しながらも、真相には突入しなかった。本書の著者浜本隆志は、事件が起きたとされる「ヨハネとパウロの日」(6/26)への疑問を手懸りに、そこへ敢て攻め込み、「東方植民」説と植民請負人ロカトールに焦点をあてる。そして、この東方植民運動の流れは⇒2022/12/17
Nobuko Hashimoto
33
阿部勤也らの先行研究を踏まえ、ネズミ捕りの男と共に消えたハーメルンの子どもたちは実際には東方植民の請負人にくっついていったという前提のもと、なぜそういえるのか、なぜハーメルンだけで悲劇として伝承されたのかを歴史資料の記述や当時の風習等から推論する。本書の特徴は、中世の伝説の検証にとどまらず、東方植民が後のドイツ史、特にナチの生存圏を求める政策に負の影響を及ぼしたことを論じているところ。前後半とも図版も豊富で文章も読みやすく、たいへん面白かった。阿部勤也の『ハーメルンの笛吹き男』、もう一度読み直そうっと。2023/03/13
ぽけっとももんが
10
グリムで有名な「ハーメルンの笛吹き男」。ところでグリム兄弟が残したのは「童話集」と「伝説集」があるそうですよ。そして笛吹き男は伝説。どうやら本当にあったことらしい。それではこどもたちはどこへ行ったのか。東方への植民説が有力、というのは目新しくはない、ただ話はそれだけではなくドイツという国の歴史や東へ向かう理由、ナチスドイツやレーベンスボルン、ヒトラーの娘たちについても記述が及ぶ。基礎知識が薄いのできちんと理解したとは言えないけれども、今まで読んだ本たちがなんとなく繋がってくる。2023/05/05
Rieko Ito
6
前半はハーメルンの笛吹き男について。笛吹き男と東方植民との関係は興味深い。ただ、なぜ子どもたちがということについては説得力に乏しい。後半は主としてナチスのレーベンスボルンについて。中世から現代までドイツに流れる東方植民政策があるという話なのだが、前半後半の結びつきには強引なところがあり、一冊の書籍としては分裂してしまっていると思う。 2024/01/24