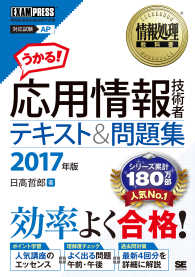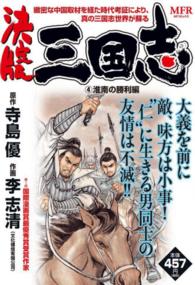出版社内容情報
労働力として有用か否かで人を選別する現代社会。障害者とその支援をする人々は「犠牲」を強いられ、「共倒れ」の連鎖が生じている。その超克を図る思想の書!
内容説明
“生きづらさ”は、あなたのせい?私たちの生を選別し、序列化し、犠牲を強いるこの社会。障害をもつ人が抱える問題に照準し、「犠牲の構造」に抗う倫理を提示する希望の書。
目次
第1章 生の無条件の肯定という企て(生の無条件の肯定とは何か;功利主義の問題点)
第2章 倫理とは何か(倫理学とはどういう学問か;共に豊かに生きる他者とは誰のことか?;「共に」生きるということ;「豊かさ」とは何か)
第3章 犠牲の問題として障害者問題を考える(障害者の問題はなぜ犠牲の問題なのか;生まれてくる生命を選別するということ;尊厳死と犠牲;いのちと選別するこの国の教育)
第4章 倫理学の再構築(トリアージ問題;人を追い込むこの社会と追い込まれている人たち;自由な主体、そして責任;権力に対峙する倫理学;「どうせ」を押しつけてくる現実にいかに抗するか)
著者等紹介
野崎泰伸[ノザキヤスノブ]
1973年兵庫県生まれ。大阪府立大学大学院人間文化学研究科博士後期課程修了・学術博士号取得。哲学・倫理学を専攻。2008年4月より立命館大学にて非常勤講師を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きくまる
4
どうしたらいい?という具体的なビジョンが見えないもどかしさは抱えつつ、社会の歪みを感じ、本当はこう考えるべきなのでは?と疑問をもつ気持ちはせめて持ち続けたい。確かに私の考え方の根本には、弱者や異質な要素を持つ人の排除につながってしまうものがある。それが無自覚なだけに、指摘されると戸惑うけれど。発達とは、異質な人や異質な考えにどれだけ多く出会えたか、大人になることは、それに対してどう対峙し、すべての人が人間的に生きられるよう責任をとること。本当に主体的に生きるとは。そしてまた成熟できない要素が見えた。2015/11/23
takao
1
「です」で終わる文章が続き、読みにくい。2021/12/16
ひつまぶし
1
功利主義に対抗的な倫理のあり方を提示するために書かれた本であると言って良いだろう。アラン・カイエ『功利的理性批判』で難解な用語で語られていたことが、障害者にまつわる事例をもとに、いくらか平易な言葉で語りなおされているような印象を受けた。功利主義批判の文脈から敷衍すれば、交換不可能なもの、譲渡不可能なものを交換・譲渡の対象にすることの問題性をあばく本書の批判的視点が重要だと思う。カイエがもう一つ明確化できていない、民主主義・贈与・共同体(そして規範)といった対抗的実践の内実を大づかみにする手応えも得られる。2021/09/21
こ~じぃ。。
1
個人に犠牲を強いる日本社会の構造自体を見直す議論を啓蒙したいんだろうな・・・2015/07/18
まつゆう
1
筆者の意見や主張において大筋では全く同意であるのだが、時折「倫理学者」としての顔を覗かせるというか、どの立場からの意見かが気になる節がちらほら(要するに穏当に過ぎるのである)。倫理的にディスアビリティの問題を論じるのではなく、障害からの倫理学を構築するのが狙いではなかったか…?2015/04/19
-

- 和書
- 朱熹文献の新研究