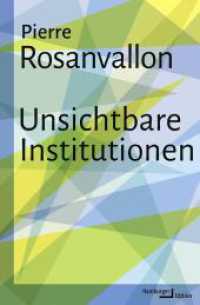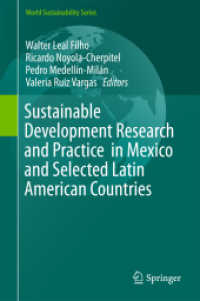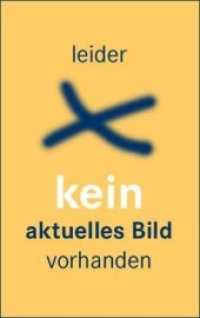出版社内容情報
我々が抱く「プライド」とは、すぐれて社会的な事象なのではないか。「理想の自己」をデザインするとは何を意味するのか。10の主題を通して迫る。
内容説明
一般に、心理学の研究対象となっている「プライド」。しかしそれに、社会学的に接近することも可能ではないか。自分に「誇り」をもつことは、まさに自他=社会関係のなかで生起する出来事であるから。プライドをもって生きることは、たえず「理想の自己」をデザインすることに等しい。わたしたちにとってそれは、夢か、はたまた悪夢か。プライド―この厄介な生の原動力に、10の主題を通して迫る社会学の冒険。
目次
第1章 自己―はじめに行動がある
第2章 家族―お前の母さんデベソ
第3章 地域―羊が人間を食い殺す
第4章 階級―どっちにしても負け
第5章 容姿―蓼食う虫も好き好き
第6章 学歴―エリートは周流する
第7章 教養―アクセスを遮断する
第8章 宗教―神のほかに神はなし
第9章 職業―初心を忘るべからず
第10章 国家―国の威光を観察する
著者等紹介
奥井智之[オクイトモユキ]
1958年奈良県に生まれる。亜細亜大学経済学部教授。1981年東京大学教養学部教養学科相関社会科学分科卒業。1988年東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。専攻は社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きいち
15
プライドは、自負とも高慢とも訳せる両義的なもの。不安定な環境で自分をポジティブに支えてくれることもある一方で、引きずられて生を台無しにすることもある。それがどれだけ社会的現象か、家族、階級、学歴、国家などプライドの源泉となる集団ごとに記述、なるほど、確かにコミュニティの代用品だ。自分の観点とは違って新鮮。◇異彩を放つのは「教養」。著者はそれを、プライドを持って生きる方法、と。職場でズタズタにされそうになっても、感情マネジメントの隘路にはまり込みそうになっても、自らを支えてくれる教養は、それぞれ構築せねば。2013/11/02
林克也
4
この本の文章表現、上から目線でいかにも学者っぽい。考え方には共感できるので嫌ではないが、気にはなる。内容には目新しいことやハッとさせられるようなことは少なかったが、十分に納得し同意でき、知識の補強材料として役に立った。印象に残ったのは、著者が「ノルウェーの森」のあの突撃隊の学生寮に住んでいたということ、つまり、あの学生寮が本当にあったということを知ったことと、この本で引用されている「暗夜行路」の直子と「ノルウェーの森」の直子が同じ直子という名前だということの意味に気付けよ!と著者が(暗に)言っていること。2013/08/31
denden_mamu
1
従ってプライドは、「生の原動力である」というだけではけっして十分ではない。同時にそれは、「死の原動力である」とも言わねばならない。創造と破壊のダイナミクスなのである。2013/08/18
hideko
1
プライドはコミュニティーの代わる役割をするの…新鮮だった。2013/08/11
たまぎょ
1
雄の孔雀の翼を広げて誇示するプライドとは違う種類のプライド(人間だけが持ちうる種類の)が存在すること、それがどこで、どういう文脈で生まれたのか、そしてどのように派生して、現在どのような状態にあるのか、それを知りたかったんだけども。社会学って心理学も哲学も政治学も、人間に関するすべてを内包する学問だと思ってた。「国のために命を捧げることは、どこの国でも最高のプライドとして位置づけられている」いや、現状はそう単純じゃないだろう。2013/08/07
-

- 洋書
- REINE