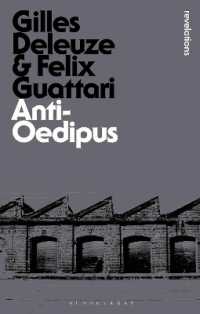出版社内容情報
経済学は科学か。彼らは何を発見し、社会にどんな功績を果たしたのか。経済学賞の歴史をたどり、経済学と人類の未来を考える。経済の本質をつかむための必読書。
内容説明
ノーベルの遺言で設立されたノーベル賞に、スウェーデン国立銀行の提案によって追加された経済学賞。その人選については、これまでも議論の的だった。はたして経済学は科学なのか。人類のどんな課題に向けて、経済学は進むべきか。そして彼らは受賞にふさわしい人物だったか。経済学賞受賞者たちの思想の系譜から、今日のわれわれが直面している問題の本質が見えてくる。混迷を深める世界経済を読み解くための必読書。
目次
第8章 古典派の復活
第9章 発明者たち
第10章 ゲームオタクたち
第11章 一般均衡という隘路
第12章 世界経済への視線
第13章 数学へのこだわり
第14章 歴史と制度
第15章 ノーベル賞再編へ向けて
著者等紹介
カリアー,トーマス[カリアー,トーマス][Karier,Thomas]
経済学者。カリフォルニア大学バークレー校でPh.D取得後、現在はイースタン・ワシントン大学教授。バード・カレッジのジェローム・レヴィ経済研究所の研究員
小坂恵理[コサカエリ]
翻訳家。慶應義塾大学文学部英米文学科卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
うえ
8
「ノーベル賞の選考に関わっていたある人物は「センは絶対に受章しない」と断言したが…予測は外れ、アマルティア・K・センは1998年にノーベル賞を受賞した。では、選考委員会が従来の方針を改めたきっかけは何だったのか。その前年の不祥事で失われたノーベル賞の威信を回復するためだった…前年の1997年にはマートンとショールズが…受賞した。ところがふたりの参加していたヘッジファンドのLTCMが、それから一年もしないうちに破綻してしまった。…しかしセンと彼の人道的な理論なら、同じ不祥事に巻き込まれる心配がなかった。」2021/10/12
Francis
5
下巻はルーカス、クズネッツ、レオンチェフ、アロー、セン、クルーグマンなどを取り上げる。相変わらず市場重視派には厳しく、そしてゲーム理論にも厳しい。もっともクズネッツ、レオンチェフなど経済データによる分析方法を編み出した経済学者には高い評価を与えている。上下通して読めば現在の経済学の動向はおおよそつかめるはず。最後の章ではノーベル経済学賞をどのように改革すべきか、著者の主張が述べられている。今話題の「21世紀の資本」の著者トマ・ピケティは果たして経済学賞を受賞できるのだろうか?2015/05/29
1.3manen
3
A.セン(1998)、P.クルーグマン(2008)、E.オストロム(2009)がこの下巻では注目できる。上巻の方は字数で書けなかった人も多い。センは飢饉の実態を調査し貧困問題の軽減や、飢饉の政治的側面に着眼して成果(154ページ~)。クルーグマンは貿易理論で貢献したが、福祉国家を支持するのが高く評価できる(181-2ページ)。オストロムはG.ハーディンの「共有地の悲劇」を検証して、保全活動の成否が分れる原因を究明した。釣りの事例で少人数の方が管理しやすく、段階的な処罰が効果を生むと解明(254ページ)。2012/11/08
takao
2
ふむ2022/09/29
ぽん教授(非実在系)
2
上巻と同様、マーケット至上主義の主流派に厳しく茶化しまくる。今後著者が第15章で書いたような形にノーベル経済学賞が変わっていくのか、それとも相変わらずなのかは注視していく必要があろう。2016/10/19