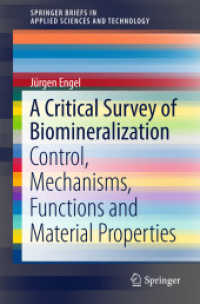内容説明
神の道を開く、巫女・神女の起源を何に求めるか。古代から近代に至るまで深く生きつづける、日本人の信仰と習俗を基底に“神”をみた人の系譜を考察する。
目次
巫女と巫娼―解説にかえて
巫女の歴史(抄)
巫女考
日本巫女史(抄)
遊女と巫女
釆女論
聞得大君論
天降り女人
神に追われて(抄)
著者等紹介
谷川健一[タニガワケンイチ]
1921年熊本県水俣市生。東京大学文学部卒。平凡社『太陽』の初代編集長をへて、1970年代に『青銅の神の足跡』や『鍛冶屋の母』などを発表し、民俗事象と文献資料に独自の分析を加え、日本人の精神的基層を研究する上での「地名」の重要性を指摘する。1981年神奈川県川崎市に日本地名研究所を設立し、所長に就任。1992年、第2回南方熊楠賞受賞。2007年、文化功労者。2013年死去
大和岩雄[オオワイワオ]
1928年長野県生。旧長野師範学校(現信州大学教育学部)卒。1952年雑誌「人生手帖」を創刊。1961年大和書房を設立。出版社経営の傍ら古代史研究に着手、季刊「東アジアの古代文化」編集主幹を務めた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
メーテル/草津仁秋斗
0
巫女に関する論を、古いものから新しいものまでまとめた本。最後に載っている谷川健一の小説風の作品もよかった。2015/12/03
momen
0
巫女の学術的研究を纏めた本。原始時代~近現代までの巫女を取り巻く環境・職務・地位の変遷と内容が具体的に説明されている。支配者や朝廷の元で働く者、民間で流浪の生活を送る巫女、琉球の政治と信仰が一体化したシステムなど取り扱う範囲は幅広い。巫女が後年遊女に変化したプロセスや理由も考察されている。巫女を扱う研究の内容を比較・批判した部分もあり資料選びの一助にもなる。記紀神話の解釈など専門的な内容も多く理解の難しいところもあるが、分量も内容も非常に濃く、巫女を取り巻く歴史の概観が十二分に把握できる良本。2023/11/14
-

- 和書
- 物理学実験 (第6版)