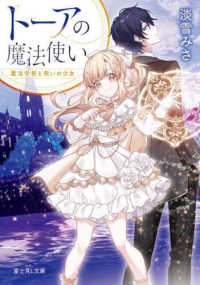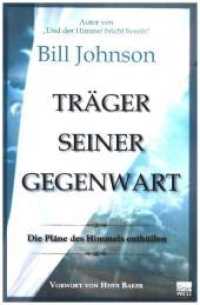内容説明
ケガレは死のケガレから出発する。ケガレ=不浄の意味はいつから始まったのか。古代から現代に及ぶ「被差別」を生む文化的要因を歴史学的、民俗学的に考える。
目次
ケガレとキヨメ―解説にかえて
民俗研究と被差別部落
賎民概説
毛坊主考
中世の「非人」
穢れの構造~聖から賎への転換
逆髪考―地獄の女王
三國連太郎・沖浦和光 対談
著者等紹介
谷川健一[タニガワケンイチ]
1921年熊本県水俣市生。東京大学文学部卒。平凡社『太陽』の初代編集長をへて、1970年代に『青銅の神の足跡』や『鍛冶屋の母』などを発表し、民俗事象と文献資料に独自の分析を加え、日本人の精神的基層を研究する上での「地名」の重要性を指摘する。1981年神奈川県川崎市に日本地名研究所を設立し、所長に就任。1992年、第2回南方熊楠賞受賞。2007年、文化功労者。2013年死去。著書に『日本庶民生活史料集成・全20巻』(共編 三一書房 1973年 第27回毎日出版文化賞)、『南島文学発生論』(思潮社 1991年 第42回芸術選奨文部大臣賞)『海霊・水の女』(短歌研究社 2001年 短歌研究賞)他
大和岩雄[オオワイワオ]
1928年長野県生。旧長野師範学校(現信州大学教育学部)卒。1952年雑誌「人生手帖」を創刊。1961年大和書房を創立。出版社経営の傍ら古代史研究に着手、季刊「東アジアの古代文化」編集主幹を務めた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
メーテル/草津仁秋斗
1
読了。大雑把に賤民、と言うしかない人たちについての論考がまとめられている。久々に読んだ「毛坊主考」の長さに驚いた。2016/07/14
momen
0
賤民身分の研究を広く浅く収録。これ一冊で賤民の歴史を概説するのではなく、有名な説や具体的な事例をちょっとづつまとめた資料集・補遺的な感じの内容で、他シリーズ本などと併読するとちょうどいい。賤民と言っても様々な職業の民がおり、社会構造からはみ出した身分だが、産業・芸能・コミュニティの支配などの役割を担い日本の文化と生活を支えてきた。時代の流れに伴い蔑視や弾圧が強くなる一方で、仏教者や民衆から支えられた一面も。地名や芸能など、現代にも賤民の活動した名残が残っていることに驚く。2024/12/07
-

- 和書
- 近世の村社会と国家