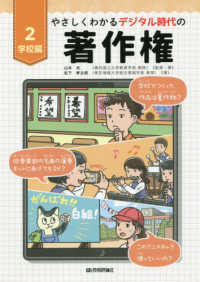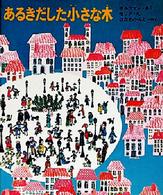出版社内容情報
民主主義は私たち一人ひとりの暮らしの中にある。元・クローズアップ現代の国谷裕子を含め、9人との対話で政治学を学び直す本。
内容説明
「自分の暮らし」をつくる、行動する政治学。
目次
1章 ボランティアから始めた人
2章 データで社会を変える人たち
3章 自治体と一緒に始めた人たち
4章 温故知新で地元をアップデートする人たち
5章 目の前の一人を幸せにして社会を変える人
6章 女性の視点から社会を変えていく人たち
座談会 これからの民主主義を考える
著者等紹介
宇野重規[ウノシゲキ]
1967年東京都生まれ。政治学者。東京大学社会科学研究所教授。東京大学法学部卒業。同大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。専門は政治思想史、政治哲学。『政治哲学へ―現代フランスとの対話』(東京大学出版会)で2005年度、渋沢・クローデル賞ルイ・ヴィトン特別賞を、『トクヴィル 平等と不平等の理論家』(講談社学術文庫)で2007年度サントリー学芸賞(思想・歴史部門)をそれぞれ受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 会社が甦る――逆境経営 7つの法則