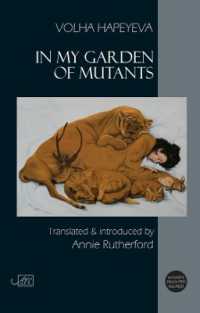- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
内容説明
知っていると安心。礼儀作法には理由がある。日本人の知恵再発見。
目次
1 礼儀作法の起源
2 出会いの作法
3 言葉の作法
4 飲食の作法
5 服装の由来
6 婚礼の由来
7 葬礼の起源
8 贈答の作法
9 年中行事の由来
10 共同体の起源
著者等紹介
樋口清之[ヒグチキヨユキ]
1909年奈良県に生まれる。文学博士。国学院大学名誉教授、国学院栃木短期大学学長、日本風俗史学会長を勤める。考古学、風俗史などの著書多数。1997年没
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。