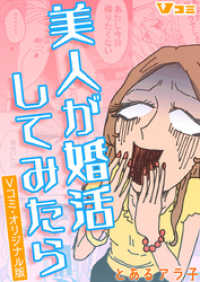- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 図書館・博物館
- > 図書館・博物館学その他
内容説明
1970年に行われた日本万国博覧会は日本人の2人に1人が訪れたという史上最大のEXPOだった。その真実に迫る。
著者等紹介
Nakawada,Minami[NAKAWADA,MINAMI]
1970年東京都港区生まれ。大阪万博研究科。建築、アート、音楽関連の執筆活動のほか、「Oscar Niemeyer20世紀最後の巨匠オスカー・ニーマイヤー」「巨匠建築家フランク・ロイド・ライト」(共にナウオンメディア)など、日本での映画監修やプロデュースを行う
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ごま
10
大判オールカラー。もう楽しくて読み始めたら一気読みだった。私が近年興味を持っている『建築』と『芸術』が詰まった本。楽しい訳だ。印象に残ったのはエクスポタワー等を手がけ、愛知万博では総合プロデューサーを務めた菊竹清訓氏のインタビュー。1人乗りの新型自動車“パーソナルチェア”の発展により建築が変わるという。それが実現した時が未来都市と言えるかもしれないというワクワクする話。残念ながら2011年に亡くなられたが、予言通りの未来を期待したい。2016/03/14
オシャレ泥棒
4
【図】確かに愛知万博は何でこんなにというくらい盛り上がらなかった印象がある。大阪万博と違って興味が持てない。娯楽の多様化などでみんながみんな同じものに熱狂することが少なくなったからかもしれないが、オリンピックは毎回盛り上がっているからなぁ…。『ぼくらが夢見た未来都市』で引き続き考える。2016/10/10
manabukimoto
2
副題の「驚愕」の名前の通り、驚きと感心の連続の大阪万博の記録。 「未来は絶対的に良くなる!」と信じることのできた時代だからこそできた、人間肯定の祝祭。 松下館の吉田五十八、住友館の大谷幸夫、鉄鋼館・自動車館の前川國男、タラカ・ビューティリオンの黒川紀章、ワコール・リッカー館のプロヂューサーには堂本尚朗の名前が! 丹下健三や岡本太郎だけでなく、伝説的な建築家が集結して、今見ても「新しい」建築がある。 おそらく、この国がもっとも輝いていた瞬間の一つが五十年前の大阪万博。醜悪なもので更新するする必要はない。2023/12/07
SUPERNEET
1
今まで、当時を生きた人々が何故大阪万博だけを神格化しているのかわからなかったが、読後もやっぱり分からなかった。リアルタイムに触れた人にしかわからないのだろうか……2008/11/10
季秋
0
こちらはパビリオン中心の一冊。夢のような面白いパビリオンたち。2023/06/03