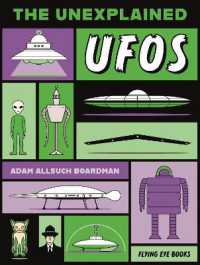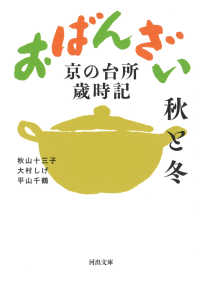出版社内容情報
*指導実績×心理学×データで培った教育メソッド
*ベネッセ総研だから伝えられる「悩み」と「解決法」
*「先生たちの先生」と言われる子ども教育のプロ
「頭のいい子になる」「スポーツできる子になる」「一芸に秀でた子になる」――これ全部、子どものある所作でわかります!
それが「質問の数」。
同じ質問ばかりする子、みかけませんか? それがいつしか、質問しなくなり、積極的に活動していたのに、
引っ込み思案になり。。。「空気でも読んでいるのかな、これも成長の一環」と本気で思っている、大人の
みなさん。それ、あなたたちのせいです!
「強引に教える」「発言させる」「(理由なく)強制させる」「押し付ける」など、大人の願望を子に植え付けてしまい、できなければすぐ叱ってしまう。昔のやり方は通用しません。
そこで、担任生活で保護者や先生たちの不安や悩みを聞く機会を増やし、学生時代に学んだ「心理学」を
もとに教育方法を変更、やがてメディアに「先生たちの先生」と言われるまでに。現在、ベネッセ総研に籍
を置いて、そこでのデータを見ながら、今を生きる親・先生たちの悩みに対して、どう解決に導くのかを全国各地で教えています。
教育者・指導者・親の3つの立場で、子どもたちがそれぞれ成長していく姿を見てわかったことが、「好奇
心が最強の育成ツール」だということ。子どものやる気を伸ばすも殺すも親次第。
本書は、親も子育てが楽しくなるように、シンプルな声かけだけど大事なことだけをまとめた「子どもの伸ばし方」。指導実績×心理学×データの掛け算でわかった珠玉のノウハウを伝えていきます。
内容説明
誰でも一度は感じたことのある子育ての悩みにぜんぶ、答えました!
目次
第1章 自分で考えて学ぶ子に育つ「教え方」(「宿題をやりなさい」と言わなくても、自らする子の親の共通点を教えてください 思うことがあっても言わずに、子どもの行動をよく見る;うちの子は新しいことに挑戦することを避けてしまいます。どうすればよいですか? 小さな挑戦を繰り返し、失敗をいい経験に変える ほか)
第2章 自分で考えて学ぶ子に育つ「比べ方」(つい、昔の自分と比較して指摘してしまいます 親のものさしで比べない;きょうだいのあいだで比べて、悪いところばかり見えてしまいます きょうだい一人ひとりの個性をおもしろがる ほか)
第3章 自分で考えて学ぶ子に育つ「見守り方」(極力言わないように見守っていますが、ちゃんとやらなくて困っています 適度な距離感を見つけて、見守ることを宣言する;いつも「どっちでもいい」と言う子になってしまいました。自分で決めてほしいのですが… ポジティブなラベルを貼って、挑戦する機会を奪わない ほか)
第4章 自分で考えて学ぶ子に育つ「機会の見つけ方」(親の見えないところで何をしているか、気になります ひとりで夢中になれる場所を認める;興味がありそうなものを買ったのに見向きもしてくれません。どうすれば? 与えるのではなく、「やりたい」を引き出す ほか)
第5章 自分で考えて学ぶ子に育つ「仲間のつくり方」(子どもの友人関係が気になります。親が介入していいのでしょうか? 同じ興味をもった仲間が自然と友達になる;好きなことに没頭してくれてうれしいのですが、親ができることはありますか? 大人から学ぶ機会をつくる ほか)
著者等紹介
庄子寛之[ショウジヒロユキ]
ベネッセ教育総合研究所 教育イノベーションセンター 主任研究員。元東京都公立小学校指導教諭。東京学芸大学大学院教育心理学部臨床心理学科修了。道徳教育や人を動かす心理が専門である。教育委員会や学校向けに研修を行ったり、保護者や一般向けに子育て講演を行ったりしている。研修・講演は年間150回以上。20年近くの教員生活で教えた児童は5000人以上。講師として直接指導した教育関係者は1万5000人に及ぶ。また、ラクロスの指導者としての顔を持ち、東京学芸大学女子ラクロス部監督、U-21女子日本代表監督、U-19女子日本代表監督を歴任。現在も本業の傍ら明治学院大学ラクロス部女子の監督を務める。子ども教育のプロとして、NHK「おはよう日本」や朝日新聞、毎日新聞などのメディアにも取り上げられた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
愛
oku y
NAGISAN
soniaclaire
しまちゃん