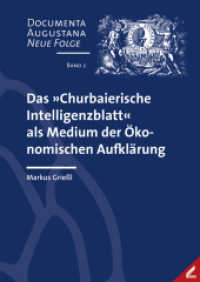出版社内容情報
「将来の収入」を上げる教育とは? 「第1志望校の最下位」と「第2志望校の1位」、どちらが有利? 子育てには「時間」をかけないといけないの? 家庭・学校・塾・職場で「人を育てる」あなたの疑問に、最新の科学がすべて答えます!
内容説明
教育や子育ては、短期的な成果よりも長期的な成果のほうが重要です。本書は、成績や受験といった「学校の中での成功」だけをゴールにはしません。学校を卒業したあとにやってくる、人生の本番で役に立つ教育とは何かを問うていきます。
目次
第1章 将来の収入を上げるために、子どもの頃に何をすべきなのか?
第2章 学力テストでは測れない「非認知能力」とは何なのか?
第3章 非認知能力はどうしたら伸ばせるのか?
第4章 親は子育てに時間を割くべきなのか?
第5章 勉強できない子をできる子に変えられるのか?
第6章 「第1志望のビリ」と「第2志望の1位」、どちらが有利なのか?
第7章 別学と共学、どちらがいいのか?
第8章 男子と女子は何が違うのか?
第9章 日本の教育政策は間違っているのか?
第10章 エビデンスはいつも必ず正しいのか?
著者等紹介
中室牧子[ナカムロマキコ]
慶應義塾大学総合政策学部教授。慶應義塾大学卒業後、米ニューヨーク市のコロンビア大学大学院でMPA、Ph.D.(教育経済学)を取得。日本銀行等を経て、2019年から現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
breguet4194q
104
エビデンスを元に、様々な状況や検証結果を説明していますが、どれも非常に説得力があります。読者が思う痒いところに手が届くようなアプローチは、言い得て妙といった感じです。更にすごいのが、エビデンスは完璧ではないと言い切っているところ。得てして勘違いされそうだが、丁寧にその理由を述べており、読者の共感をきちんと得ていると思いました。子育てのベースの考え方として、知っておきたい内容が満載です。2025/07/20
よしたけ
43
読了してきた子育て本の寄せ集め感に感じ、真新しい知識はあまり得られなかったが、才能診断、気質診断など、子供の性質を見抜くテストが幾つか用意されているのは面白い。興味深かった記述: 共通点・能力の近い友人を選んでしまうので、無理にレベルの高い環境に放り込むのはむしろ逆効果/自らがトップ層にいられる環境の方が自己肯定感高まり受験結果も良い/テストでは他者比較でなく前回比較でどれだけ改善しているかをフィードバックせよ/幼児教育は好影響の場合と同様、悪影響 であっても長期にわたって持続する2025/03/12
レモン
37
『「学力」の経済学』が面白かったので、期待値が高かった本書。デジタル教材は習熟度別指導のツールとして効果的であったり、スポーツの良い効果など興味深いテーマがたくさんあったが、再現性のない実験が多いことに驚いた。エビデンスは絶対に覆らない決定版ではないとのことなので、早生まれの息子も不利なスタートなど気にせず育っていって欲しい。非認知能力向上のための具体的なノウハウが知りたい。幼児教育の質の高低が親には知り得ないのが何とも残念。保育園の場合は入れたい園があっても、希望通りにならないケースが多い点が悩ましい。2025/04/29
ta_chanko
24
スポーツ・音楽・美術に取り組むことやリーダーの経験を積むことは、「非認知能力」を高める。子どもと過ごす時間の質を高めると、学力が高まる。学力を高める三つの要素=目標を立てる・習慣化する・チームで取り組む。「鶏口となるも牛後となるなかれ」は正しい。習熟度にあった指導が大切。教育行政は、何をするかではなく、何をしないかを決めることが大事。PCに先生の代わりはできない。学力と非認知能力の両方を伸ばせる先生は少ないが、存在する。2025/02/25
金城 雅大(きんじょう まさひろ)
19
興味深い話題もありつつさらっと読めました。深掘りする読書会が楽しかった〜2025/03/15