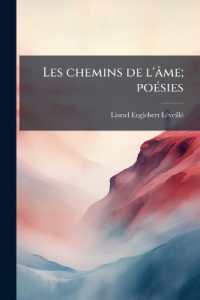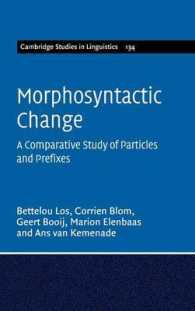出版社内容情報
植原 亮[ウエハラリョウ]
著・文・その他
内容説明
本書では、遅く考えること―意識的にゆっくり考えることを「遅考」と呼ぶ。それを使いこなす方法こそ、「遅考術」である。レッスンを通じて、思考の間違いを回避し、よりよい思考を生み出す技を身につけよう。豊富な「練習問題」や、先生と生徒たちの「対話」によって、自力で「深い思考」に到達できる。
目次
1 「遅く考える」とは?
2 思考には2つのモードがある
3 早とちりのメカニズムをつかむ
4 ゆっくり「言葉」を考える
5 因果関係がわかれば、思考の質はもっと高まる
6 まぎらわしい因果関係に対処する
7 新たな解決策を考え抜く
8 本当の原因を突き止める
9 思考の精度がグッと高まる、3つの考え
10 怪しい話に惑わされないために―総合演習
著者等紹介
植原亮[ウエハラリョウ]
1978年埼玉県に生まれる。2008年東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。博士(学術、2011年)。現在、関西大学総合情報学部教授。専門は科学哲学だが、理論的な考察だけでなく、それを応用した教育実践や著述活動にも積極的に取り組んでいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
-
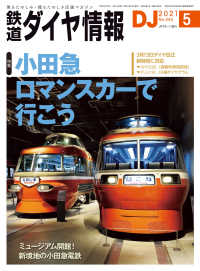
- 電子書籍
- 鉄道ダイヤ情報2021年5月号 鉄道ダ…