出版社内容情報
「この一冊だけでいい。」
100年後にも残る、「文章本の決定版」を作りました。(担当編集者:柿内芳文)
内容説明
プロの「書く人」になるために。ひとりでも多くの人を喚起する「原稿」をつくるために―。取材とは、インタビューのことではない。一冊の本のように「世界を読む」ところからすべては始まる。執筆とは、「書くこと」である以上に「考えること」。センスでなく思考のみが、達意の文章を生み出す。推敲とは、原稿を二段も三段も高いところまで押し上げていく行為であり、己の限界との勝負である。
目次
ガイダンス ライターとはなにか
取材(すべては「読む」からはじまる;なにを訊き、どう聴くのか;調べること、考えること)
執筆(文章の基本構造;構成をどう考えるか;原稿のスタイルを知る;原稿をつくる)
推敲(推敲という名の取材;原稿を「書き上げる」ために)
著者等紹介
古賀史健[コガフミタケ]
ライター。1973年福岡県生まれ。九州産業大学芸術学部卒。メガネ店勤務、出版社勤務を経て1998年にライターとして独立。2014年、ビジネス書ライターの地位向上に大きく寄与したとして、「ビジネス書大賞・審査員特別賞」受賞。翌2015年、「書くこと」に特化したライターズ・カンパニー、株式会社バトンズを設立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひろき@巨人の肩
110
まさにライターの教科書。ライターとは、取材した対象への「返事」をコンテンツ化する仕事。取材・執筆・推敲を繰り返しコンテンツを作り続ける。ライフワークとして「ライター」と名乗りたくなった。「読まれたくない文章を書かない」というポリシーのもと「ジャンルではなくスタイル」を確立するという意識で実践あるのみ。書くことに悩んだときに何度も手に取りたい。2022/07/20
よしたけ
51
文章を書く、想いを伝える。人として基本かつ重要な力だが、本書はこれらの鍛錬に最適。まず「書く力」でなく「読む力/聞く力」を鍛える(インプットができない人間が伝えることなどできない)、「情報をジャッジする力」を身につける(TVをながら見しても何も得られない、想像力を働せえ読書をし要約を他人に伝える練習)、投げっぱなしの質問をしない(相手に任せきりで考えることを放棄した質問は失礼。質問はよく練られるべき)、推敲時は見た目を変える(縦書き原稿なら横書きにしてフォントも変えることで新鮮な気持ちで見直せる)等々。2021/10/12
Nobu A
36
HONZ推薦本。21年刊行。古賀史健著書初読と思いきや、岸見一郎共著「嫌われる勇気 自己啓発の源流『アドラー』の教え」を読んでいた。書き方指南書は数冊読んでいるが、本書は他書とは一線を画す。売上を意識し巧みに伝えるのを生業としているライター視点からの「書くこと」の本質に迫ったもの。「知的格闘」等と喩えられる書く作業。学者宛らのメタファー論は瞠目。桃太郎の漫画を使った構成論も秀逸。また「木工接着剤」等、随所に独特な比喩に練った跡。畢竟、各段階で全方位に意識を向ける必要がある。とても勉強になった。久々の良書。2024/02/21
ロクシェ
33
最低5回は読み返すべき本にはじめて出逢えた。本書は文章ではなく「原稿」を「書き上げる」ための技術論や方法論が満載な『書く人の教科書』だ。ライターとは取材者でありコンテンツを作る人。何かを知ろうとすることはすべて取材。「情報の稀少性」「課題の鏡面性」「構造の頑強性」の3つを兼ね備えたとき、ただの文章がコンテンツに変わる。取材と執筆を経て書き終えた原稿は、推敲によって「書き上がる」。構造の頑強性を考えるための、桃太郎の絵を30枚→10枚に厳選するワークがわかりやすかった。何度も読み返したい、最高の教科書です。2022/04/18
九曜紋
26
税込3300円という価格、480ページという分厚さに購入を躊躇したが、読んでよかった。10年後、20年後、さらには100年後にも色褪せない「ライターの教科書」となるよう、3年の月日をかけた本書。著者の魂が込められている。「書くこと」を生業とする著者の覚悟、矜恃、使命感に裏打ちされた考察と、その成果の惜しみない開示に拍手を贈りたい。私のこれからのささやかな文章作成活動にも活かしていきたい。 2021/08/01
-

- 電子書籍
- 真・上京シェアハウス~彼女と幼馴染と知…
-
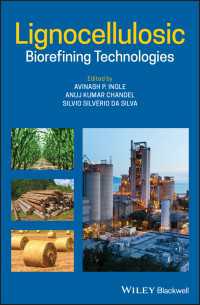
- 洋書電子書籍
- Lignocellulosic Bio…







