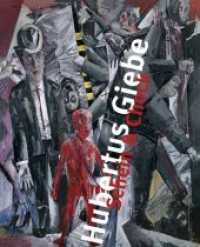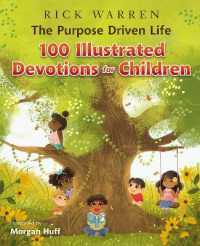内容説明
主流派経済学の実験場としての日本―その主なる要因となった「経済ポピュリズム」、そして「サイレント・マジョリティ」とは何か?No.1アナリスト(日経ヴェリタスエコノミストランキング2017年~19年・債券部門第1位)が、経済学の源流から直近の金融政策までをつぶさに追い、分析と洞察を重ねた意欲作。
目次
第1章 主流派経済学の起源
第2章 市場至上主義の時代
第3章 経済学の黄昏
第4章 金融政策の本質
第5章 日本経済という実験場
第6章 社会の中の中央銀行
第7章 経済ポピュリズム
第8章 経済学の未来
著者等紹介
森田長太郎[モリタチョウタロウ]
SMBC日興証券チーフ金利ストラテジスト。慶應義塾大学経済学部卒業。日興リサーチセンター、日興ソロモン・スミス・バーニー証券、ドイツ証券、バークレイズ証券を経て2013年8月から現職。日本の国債市場に30年近くにわたり関わる。グローバル経済、財政政策、金融政策の分析などマクロ的アプローチに特色を持つ。日経ヴェリタス債券アナリストランキングは第1位(2017年~2019年)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まゆまゆ
14
90年代から多く語られるようになった金融政策は経済ポピュリズムともいうべき潮流に呑み込まれていった結果、本来の役割を果たしていないのではないか。そもそも金融政策はリスクプレミアムを強制的に発動させることであり、量的緩和政策がいかに効果がなかったかを語っていく。インフレターゲットも効果があるのかないのか……中央銀行が無くとも金利は市場を通じて決まっていくが、そこへ介入することにどれほどの効果があるのか、未だによく分からない……2019/11/28
Iwata Kentaro
5
金融政策が思ったように行かない中、そもそも経済学は学問たりえるのか、という疑問をきちんと看破した偉い本。ノーベル経済学賞って「存在しな」かったんですねー。学問の世界で異論が出るのは分かるけど経済学者の意見合わなすぎで、イデオロギーが強すぎだよなーとは昔から思ってました。2019/12/08
A.Sakurai
4
債券市場の専門家が見る経済学の現状。超意訳するとリフレ派主導による日銀の金融政策はクソ!ということを述べるためにアダム・スミスから説き起こす。経営学の流れや社会科学としては異様な特質、政治や社会との関わりなど幅広い視野で独自の解釈を交えて論じている。進化心理学など周辺分野の解釈などは突っ込みたい部分もあるが、総じて学際的な視点は面白い。際立つのはやはり専門の金利の解釈。中央銀行は金利を制御するのが役割。金融政策は現在と将来の需要のやり取りに当たる。金融緩和は財政出動と同じく負担の先送りなのだとする。2020/12/27
kousan
4
イギリス哲学や最新のAIの動向まで織り込んで、経済学というものに迫ろうとする意欲作であり、2019年の経済本では非常に高評価を得ているのも頷ける。良書。2020/01/05
Akiro OUED
3
1990年代後半以降、日本は主流派経済学の実験場になってる。異次元の金融緩和は、縮こまった日本経済に着火しないし、一人10万円の強制給付も貯蓄されただけ。いくらお金を配っても、毎日6食も食えないし、自宅は一軒で十分だ。やっぱり、MMTを前提にするヘリマネ政策は破綻する。好著。2023/02/04