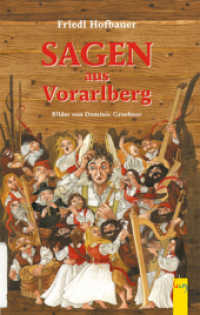内容説明
明治より近代国家への発展を支えた日本の養蚕。戦後、急速に衰退したその高い技術が南インドで地域経済に大きな貢献をしている。だが、ここまでの道程は平坦ではなかった。技術移転や技術指導は文化と文化の衝突である。現地の風土にあわせた技術と知識の継承により高品質な生糸づくりをめざして奮闘した長期にわたるプロジェクトの報告。
目次
プロローグ 日本の養蚕技術の継承:一線級の人材を投入した国際協力プロジェクト
第1章 マユはどうやってできるのか:カイコのライフサイクル50日
第2章 二化性養蚕プロジェクトの目標:良質の生糸をつくるために
第3章 南インド養蚕前史:熱帯二化性養蚕技術確立への長い道のり
第4章 プロジェクト第1期~第2期:研究所の技術開発から現場での技術実証へ
第5章 プロジェクト第3期:新しい二化性養蚕技術、本格的普及拡大へ
第6章 プロジェクト16年の成果:二化性養蚕技術協力による地域の総合的発展
第7章 プロジェクトの自立発展:コラールゴールド、回転まぶし、面的拡大
第8章 プロジェクトからの示唆と教訓:南インドと世界の養蚕の今後
エピローグ インド養蚕協力が残したもの
著者等紹介
山田浩司[ヤマダコウジ]
国際協力機構(JICA)研究所参事役。1963年生まれ。岐阜県出身。上智大学大学院経済学研究科、日本福祉大学大学院国際社会開発研究科修了。民間金融機関勤務を経て1993年JICA入構。ネパール事務所、アジア第二部勤務の後、2000年より世界銀行出向。2003年JICA復帰、国際協力総合研修所調査研究グループ副主任研究員。2007年インド事務所次長を経て、2010年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Sanchai
しほ
Yoshiki Ehara
周利槃特